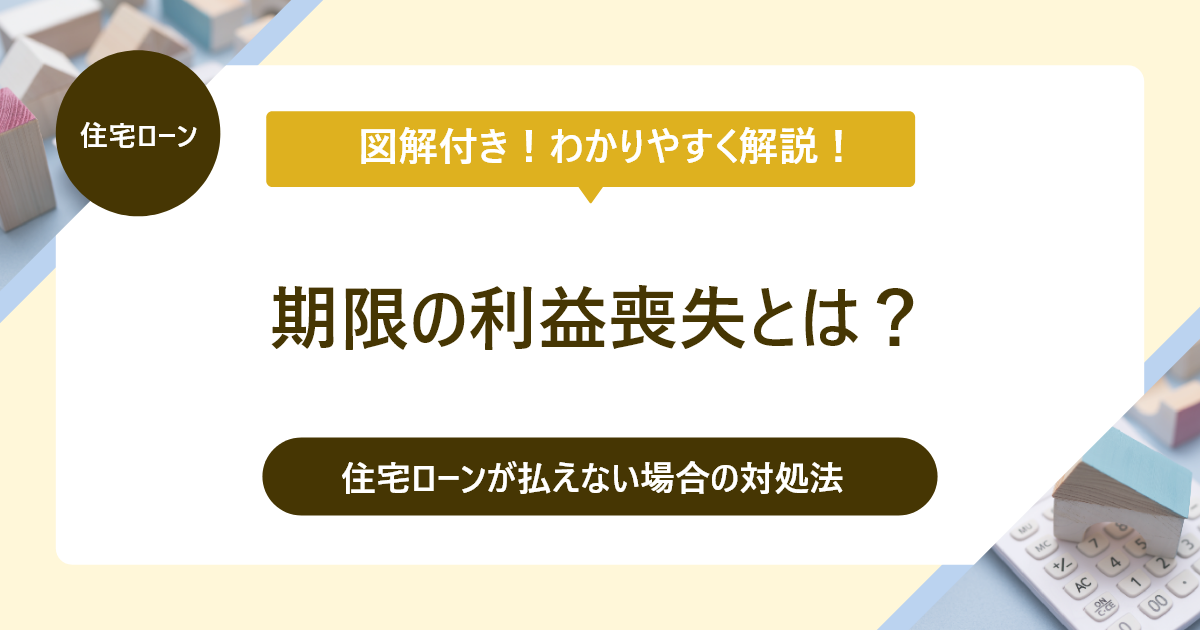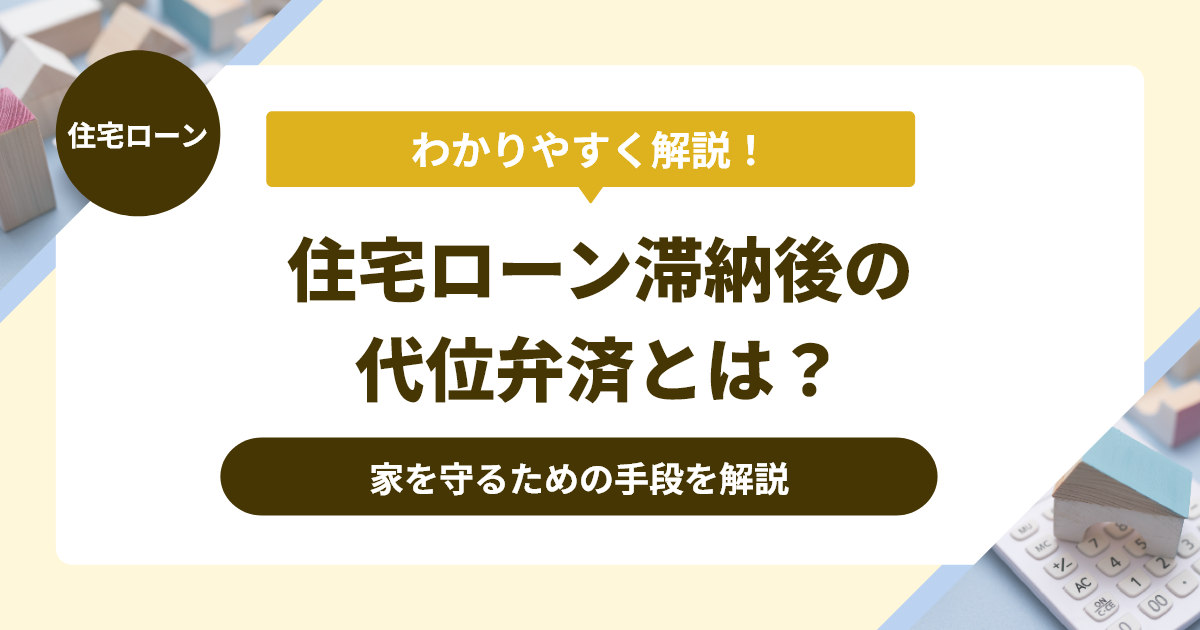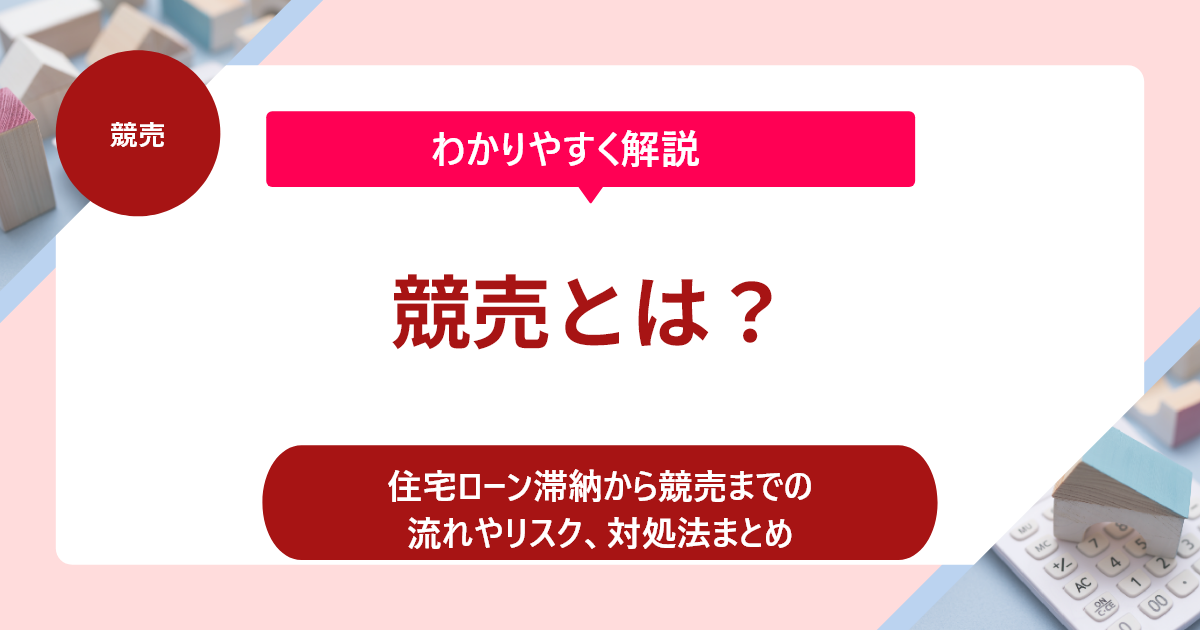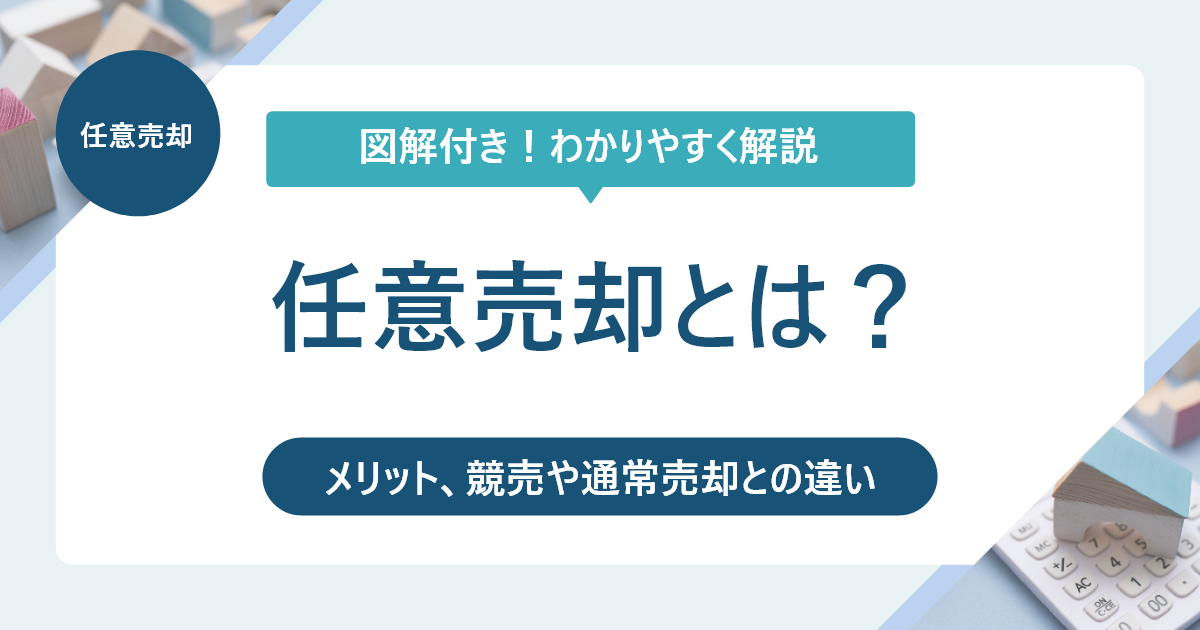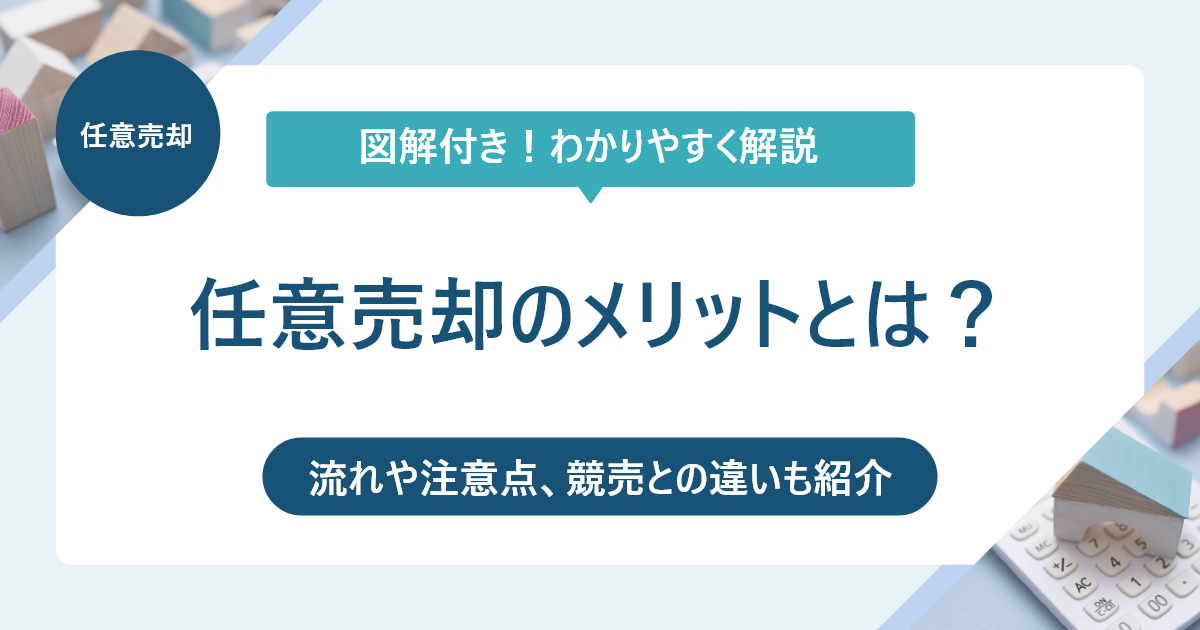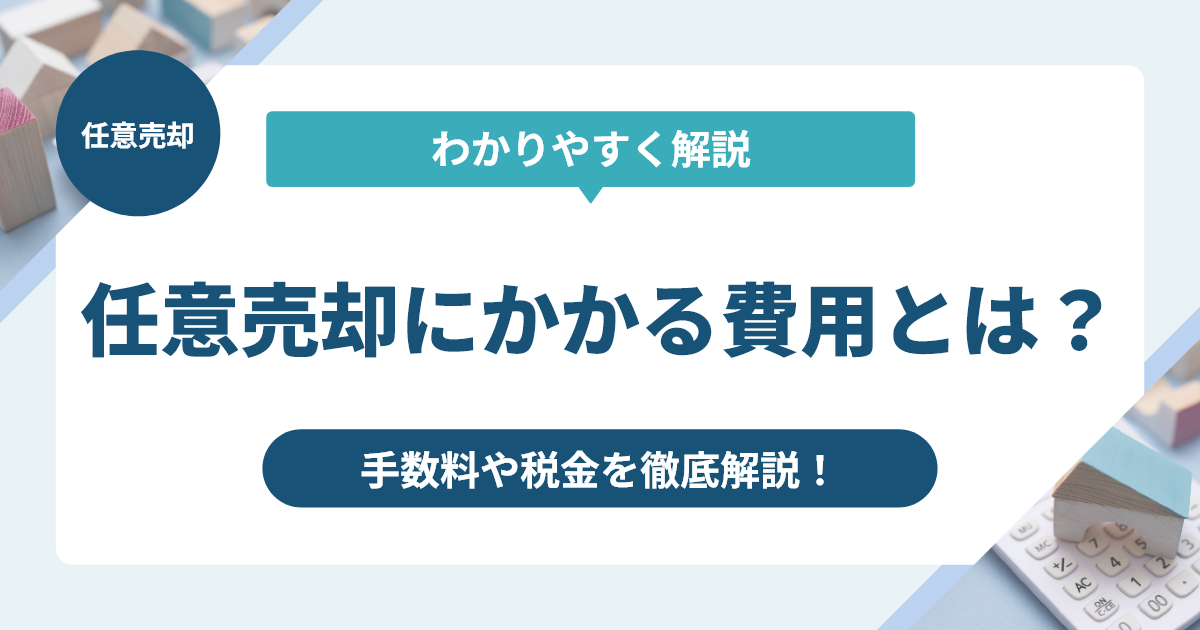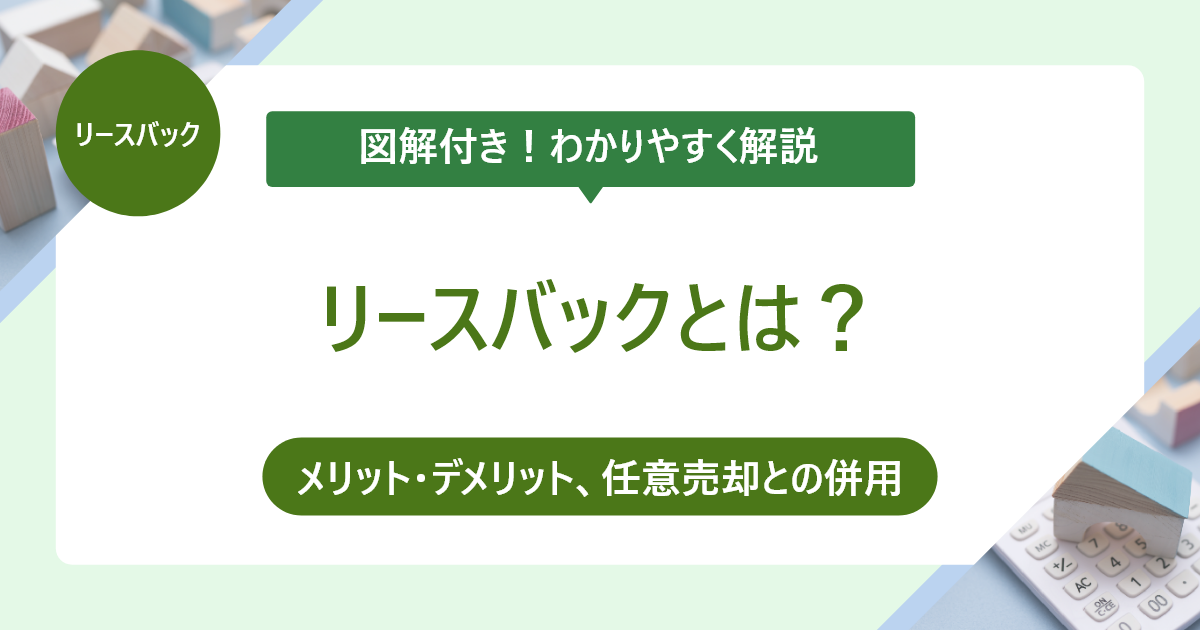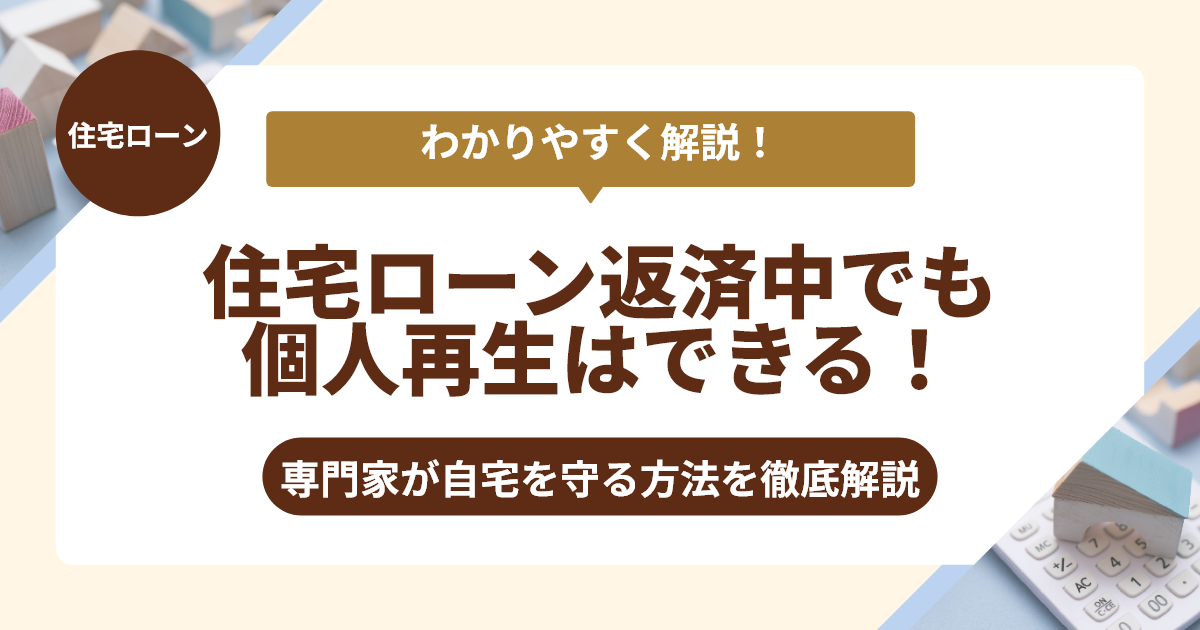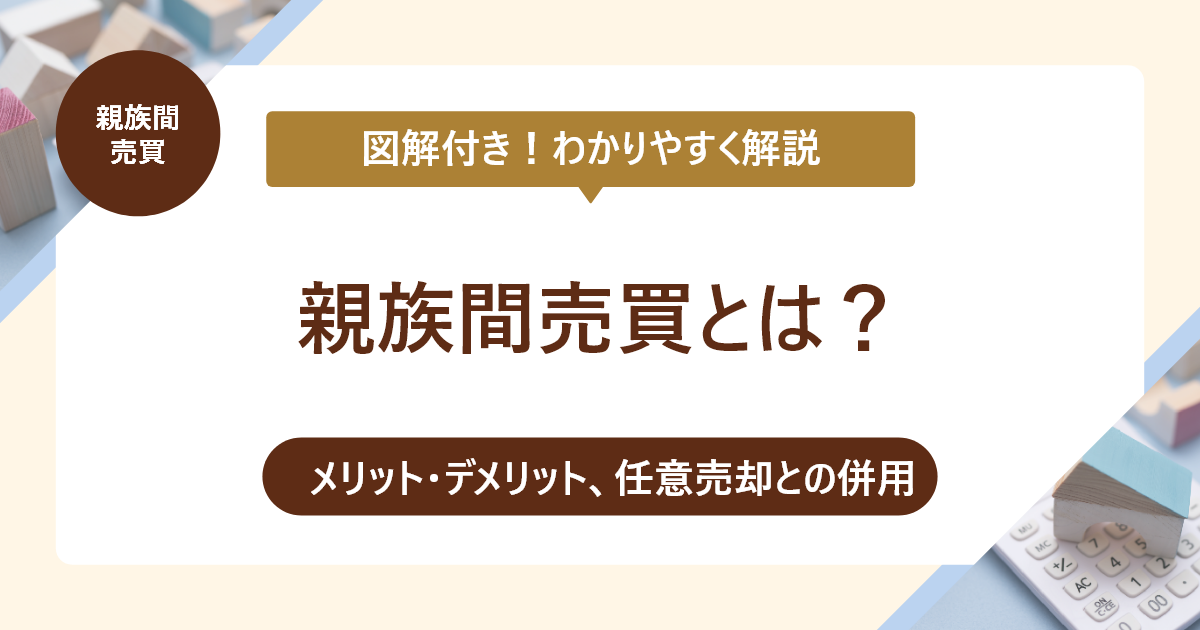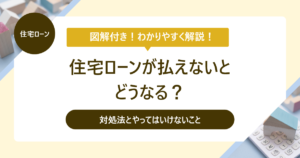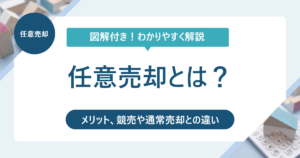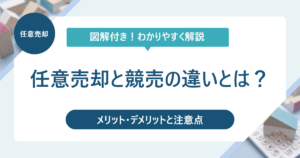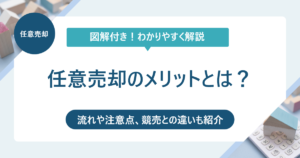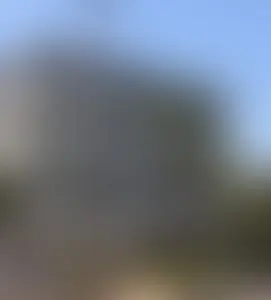病気や怪我で住宅ローン払えない!団信・公的制度と家を守る対処法5選
更新日 2025-12-23
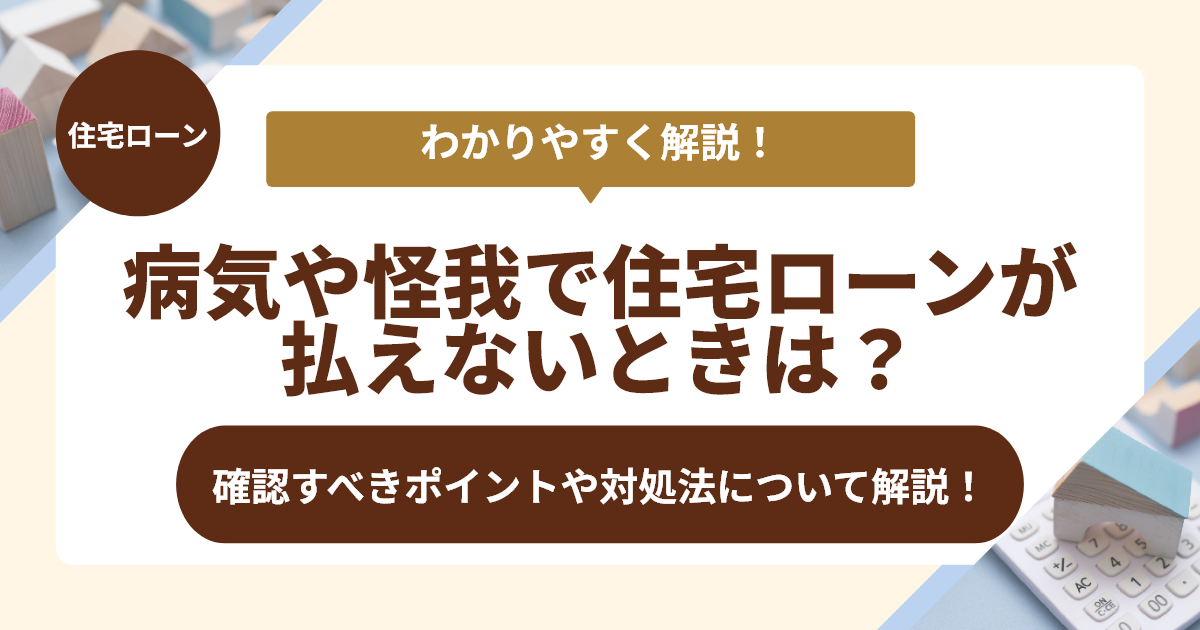

病気やケガで収入が減り、住宅ローンの支払いが難しくなった。このままでは家を手放すしかないのか。滞納が続くのは避けたい。こうした悩みを抱える方は少なくありません。
家族に迷惑をかけたくないと、一人で対策を探している方も多いでしょう。実際、団信や医療保険、公的制度が利用できるケースも多く存在します。
本記事では、病気で住宅ローンが払えない場合に今すぐ確認すべき保障・公的制度から、それらが使えない場合の具体的な対処法、そして家を残す方法まで、専門家の視点から徹底的に解説します。
病気で住宅ローンが払えない…まず確認すべき5つの保障・公的制度

病気やケガで収入が減り、住宅ローンの支払いが困難になったとしても、すぐに家を手放す必要があるとは限りません。実は、多くの方が利用できる保障や公的制度が存在しますが、その存在を知らずに一人で悩んでいるケースが非常に多いのです。
ここでは、病気で住宅ローンが払えない状況になった際に、まず確認すべき5つの保障・公的制度について詳しく解説します。これらの制度を活用できれば、住宅ローンの返済を継続できる可能性が高まります。
1. 団体信用生命保険(団信)|「高度障害」や「疾病特約」の対象か
住宅ローンを組む際、ほとんどの方が加入している団体信用生命保険(団信)。この団信が、病気で住宅ローンが払えない状況を救う最も強力な保障となる可能性があります。
団信は、住宅ローン契約時に金融機関が加入を義務付ける保険で、契約者が死亡または高度障害状態になった場合、住宅ローンの残債が全額保険金で支払われる仕組みです。つまり、条件に該当すれば住宅ローンの返済義務が完全に免除されます。
高度障害状態とは

高度障害とは、病気やケガにより身体機能が大きく損なわれ、日常生活が困難になる状態を指します。具体的には、以下のような状態が該当します。
両目の視力を完全に失った状態では、視力の測定ができない場合や、明暗が弁別できない程度の視力になった場合が該当します。言葉を話す能力や咀嚼機能を完全に失った状態では、音声や言語機能を完全に失った場合、食物を噛み砕いて飲み込むことができなくなった場合などが含まれます。
重度の脳障害や内臓疾患により継続的な介護が必要な状態では、常時介護が必要で、日常生活の基本的な動作を自分で行えない状態が該当します。両腕・両足をそれぞれ手首・足首より上で失うか、完全に機能を失った状態、または片腕を手首より上、片足を足首より上で失うか、両方の機能を失った状態なども高度障害に含まれます。
上記の高度障害状態に該当し、団信に加入していれば、住宅ローンの残債が全額保険金で補償されます。これにより、病気で収入がなくなっても、家を失う心配はありません。
疾病特約(三大疾病・八大疾病保障)
近年、多くの金融機関では、通常の団信に加えて「疾病特約」付きの団信を提供しています。これは、がん・急性心筋梗塞・脳卒中の三大疾病や、さらに範囲を広げた八大疾病(三大疾病に加えて高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎)をカバーする保障です。
疾病特約の保障内容は金融機関によって異なりますが、一般的には以下のようなケースで住宅ローン残債が保険金で支払われます。がんと診断された場合は診断確定時点で保障が適用されることが多く、急性心筋梗塞や脳卒中で所定の状態が60日以上継続した場合、その他の疾病で就業不能状態が一定期間(12ヶ月など)継続した場合などに保障が受けられます。
自分が加入している団信に疾病特約が付いているか、どのような条件で保障が受けられるかを、今すぐ確認しましょう。住宅ローンの契約書や、金融機関から届いている保険証券に記載されています。
2. 債務返済支援保険・就業不能保険|働けない間の返済を補填
団信以外にも、病気で住宅ローンが払えない状況をサポートする保険があります。それが「債務返済支援保険」と「就業不能保険」です。
債務返済支援保険
債務返済支援保険は、病気やケガによる収入減に備える保険で、住宅ローンの返済を直接サポートしてくれる保険です。
一般的には、30日以上の長期療養を余儀なくされた場合に保険金が支払われ、1回の入院で最大25ヶ月程度、住宅ローンの返済金相当額を補償してくれます。この保険があれば、入院中や療養中も住宅ローンの滞納を防ぐことができます。
ただし、補償内容は保険会社や契約内容によって異なるため、具体的な補償期間や支給条件を確認しておく必要があります。
就業不能保険
就業不能保険は、医療保険に付帯していることが多い保険で、病気やケガで長期間働けなくなった際に給付金を受けられる保険です。一時金や年金、月払のいずれかで支給されるのが一般的です。
例えば、就業不能状態が60日以上継続した場合、1年5ヶ月までは短期就業不能給付金として毎月一定額が支給され、1年6ヶ月以降は長期就業不能給付金として異なる金額が毎月支給されるといった形です。
就業不能保険は住宅ローン返済を直接補償する保険ではありませんが、給付金を住宅ローンの返済に充てることで、滞納を防ぐことができます。加入している医療保険の内容を確認し、就業不能保険が付帯しているかどうか、どのような条件で給付されるかを把握しておきましょう。
3. 公的医療保険|「傷病手当金」で給与の約2/3を受給
健康保険に加入している会社員や公務員の方は、病気やケガで働けなくなった場合、「傷病手当金」という公的制度を利用できます。これは、病気で住宅ローンが払えない状況を支える非常に重要な制度です。
傷病手当金の概要
傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事を休み、給与が支払われない場合に、最長1年6ヶ月間にわたって給付金を受け取れる制度です。支給額は給与の約3分の2で、家計を見直せば住宅ローンの返済を継続できる可能性があります。
注意点として、国民健康保険に加入している自営業者やフリーランスの方は、この制度の対象外となります(一部の国民健康保険組合を除く)。また、会社から給与が一部でも支払われている場合、その差額のみが支給されます。
申請方法と支給例
傷病手当金の申請先は、健康保険組合または協会けんぽ(全国健康保険協会)です。申請には、医師の診断書、事業主の証明書、本人の申請書などが必要となります。
具体的な支給例を見てみましょう。月給30万円の場合(直近12ヶ月分の平均月収)、1日あたり約6,667円(30万円÷30日×2/3)が支給されます。月額にすると約20万円となり、この金額を住宅ローンの返済に充てることで、滞納を回避できる可能性があります。
ただし、労災保険と重複する場合は調整が行われるため、両方を同時に受給できない場合もあります。詳細は加入している健康保険組合に確認しましょう。
参照:全国健康保険協会
4. 労災保険|業務中・通勤中の病気やケガが原因の場合
業務中や通勤中に発症した病気やケガが原因で住宅ローンが払えない状況になった場合、労災保険(労働者災害補償保険)が適用されます。
労災保険の対象となる労働者
労災保険は、業種・規模に関係なく、1人でも労働者を雇用している事業所が加入を義務付けられています。正社員だけでなく、アルバイトやパートなど、雇用形態を問わず全ての労働者が対象となります。
業務中の事故やケガ、業務が原因で発症した病気(過労死、職業病など)、通勤中の事故やケガなどが労災保険の適用範囲です。
労災保険の給付内容
労災保険では、「休業補償給付」として平均賃金の60%が支給されます。さらに「休業特別支給金」として20%が追加支給されるため、合計で平均賃金の約80%の補償が受けられます。
傷病手当金の約67%と比較すると、より手厚い補償となっています。また、療養費用も全額補償されるため、医療費の負担もありません。
労災保険の申請は、勤務先を通じて労働基準監督署に行います。業務との因果関係を証明する必要があるため、発症の経緯を詳しく記録しておくことが重要です。
5. 障害年金|病気やケガによる障害が長期化する場合
病気やケガによる障害が長期化し、日常生活や仕事に支障をきたす状態が続く場合、「障害年金」を受給できる可能性があります。
障害年金の種類
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。国民年金に加入している方は障害基礎年金、厚生年金に加入している方は障害厚生年金が支給されます(障害基礎年金も含む)。
障害の程度によって等級が分かれており、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級の等級があります。等級によって支給額が異なります。
支給例と申請方法
例えば、障害基礎年金2級の場合、年額約78万円(月額約6.5万円)が支給されます。障害厚生年金の場合は、これに加えて報酬比例部分が上乗せされるため、より多くの金額を受け取ることができます。
この障害年金を住宅ローンの返済に充てることで、支払いを継続できる可能性がありの認定基準は複雑なため、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
保険や制度が使えない…住宅ローンが払えない時の対処法

前章で紹介した保険や公的制度が利用できない、または給付額では住宅ローンの返済をカバーできない場合でも、諦める必要はありません。病気で住宅ローンが払えない状況に対して、取るべき具体的な対処法が複数存在します。
ここでは、保険や制度が使えない場合に検討すべき3つの対処法について、それぞれのメリット・デメリットとともに詳しく解説します。
1. まずは金融機関へ返済相談(リスケジュール)

病気で住宅ローンが払えない状況になった際、最優先で行うべきは金融機関への相談です。滞納する前、できれば支払いが厳しくなりそうだと感じた時点で、早めに連絡することが重要です。
リスケジュール(リスケ)とは
リスケジュールとは、住宅ローンの返済計画を見直し、月々の返済負担を軽減する方法です。金融機関と交渉することで、返済条件を変更してもらえる可能性があります。
具体的には、返済期間を35年から40年に延長することで月々の返済額を減らしたり、一定期間は利息のみを支払い元本の返済を据え置く方法があります。また、一時的にボーナス払いを停止して月々の返済額を平準化する方法もあります。
リスケジュールのメリットとデメリット
リスケジュールのメリットは、月々の返済額を減らすことで当面の支払いを継続できること、滞納を回避でき、信用情報に傷がつかないこと、自宅を手放さずに済むことなどが挙げられます。
一方でデメリットもあります。返済期間が延びることで、最終的な支払総額は増加します。金融機関の審査があり、将来の収入回復が見込まれることが条件となります。また、一度リスケジュールを行うと、再度の条件変更が難しくなる場合があります。
リスケジュールが認められやすいケース
リスケジュールは、一時的な収入減で、回復の見込みがある場合に認められやすい傾向があります。病気の治療が終われば仕事に復帰できる見込みがある場合、傷病手当金や障害年金の受給が決まっており一定の収入が見込める場合、配偶者の収入で最低限の返済ができる場合などは、金融機関も前向きに検討してくれる可能性が高いです。
返済が厳しくなったら、まず金融機関に相談し、リスケジュールの可能性を探りましょう。滞納してから相談するよりも、滞納前に相談する方が、金融機関の対応も柔軟になります。
2. 親族からの支援や借り入れを打診する

金融機関のリスケジュールが難しい場合、または一時的な資金が必要な場合、家族や親族に支援を依頼するという選択肢もあります。
親族からの借り入れのメリット
親族からの借り入れには、無利息または低金利で借りられる可能性があること、返済条件を柔軟に設定できること、金融機関の審査が不要なことなどのメリットがあります。
病気の治療期間中だけ支援してもらい、職場復帰後に返済するといった柔軟な計画を立てることが可能です。
注意すべきポイント
ただし、親族間の金銭のやり取りには注意が必要です。金利や返済計画を明確にしないと、贈与とみなされ課税されるリスクがあります。年間110万円以上を無償で受け取った場合、贈与税の対象となります。
贈与税を避けるためには、借用書を作成し金利を設定する(無利息ではなく、最低でも0.1%程度の金利を設定)、返済計画を明確にし、実際に返済を行う記録を残す、銀行振込など客観的な証拠が残る方法で返済するといった対策が必要です。
その他の金融支援
親族からの借り入れが難しい場合、信用金庫や信用組合の融資を検討する方法もあります。一般の銀行よりも審査に通りやすく、年収基準が緩い場合があります。地域密着型の金融機関なので、個別の事情を考慮してくれる可能性が高いです。
ただし、融資まで時間がかかることがあるため、早めに相談することが重要です。
3. 家の売却を検討する(アンダーローンの場合)

病気の回復が見込めず、長期的に住宅ローンの返済が困難な場合、家の売却という選択肢も検討する必要があります。
アンダーローンとは
アンダーローンとは、家の売却価格が住宅ローンの残債を上回っている状態を指します。この場合、家を売却することで住宅ローンを完済でき、さらに手元に資金が残る可能性があります。
家を売却するメリット
家を売却するメリットとして、売却価格がローン残債を上回れば、完済後に資金が手元に残ることがあります。この資金を新居購入費用や引っ越し費用、当面の生活費に充てることができます。また、住宅ローンの返済義務から完全に解放され、精神的な負担が軽減されます。病気の治療に専念できる環境を作ることができます。
さらに、固定資産税や管理費、修繕積立金などの維持費用も不要になるため、家を所有していることによる経済的負担がなくなります。
家を売却するデメリット
一方、デメリットも存在します。住み慣れた家を手放すことになり、精神的な喪失感があります。売却には仲介手数料(売却価格の3%+6万円程度)、登記費用、引っ越し費用などがかかります。買主が見つかるまでに数ヶ月かかる場合があり、すぐに資金化できないこともあります。売却後の住まいを確保する必要があり、賃貸物件の契約には初期費用が必要です。
売却を検討すべきケース
家の売却を検討すべきケースとして、病気の回復が見込めず、長期的に収入減が続く見通しの場合や、現在の家が広すぎる、または維持費が高すぎる場合、売却すればローンを完済でき、手元に資金が残る場合(アンダーローン)などが挙げられます。
売却を決断する前に、必ず不動産会社に査定を依頼し、現在の市場価格を把握しましょう。複数の不動産会社に査定を依頼することで、より正確な相場を知ることができます。
【危険】病気で住宅ローンを滞納し続けると「競売」で家を失う

病気で住宅ローンが払えない状況を放置すると、最終的には「競売」という最悪の事態に発展します。競売になると、市場価格よりも大幅に安い価格で家を失い、多額の借金だけが残るという悲劇的な結果を招くことになります。
ここでは、滞納から競売までの流れと、競売を避けるための「任意売却」について詳しく解説します。
1. 滞納から競売までの流れ
住宅ローンの滞納が続くと、以下のような流れで競売手続きが進んでいきます。
滞納1〜2ヶ月目:督促状の送付
住宅ローンの支払いが遅れると、まず金融機関から督促状が届きます。この段階では、まだ返済の意思があることを示せば、リスケジュールなどの相談に応じてもらえる可能性が高いです。この時点で相談することが、最も重要です。
滞納3〜6ヶ月目:期限の利益喪失
滞納が3〜6ヶ月続くと、「期限の利益喪失通知」が届きます。これは、「分割払いの権利を失った」ことを意味し、住宅ローンの残債全額を一括で返済するよう求められます。
ほとんどの方は一括返済できないため、この時点で事実上、住宅ローンの返済が不可能な状態になります。
あわせて読みたい
滞納6〜8ヶ月目:代位弁済
一括返済に応じられない場合、保証会社があなたに代わって金融機関にローン残債を一括で支払います。これを「代位弁済」と呼びます。
代位弁済が行われると、債権者が金融機関から保証会社に移ります。保証会社は、代位弁済した金額をあなたに請求してきます。この段階になると、リスケジュールなどの交渉はほぼ不可能になります。
あわせて読みたい
滞納8〜10ヶ月目:競売申立て
保証会社からの請求にも応じられない場合、保証会社は裁判所に競売の申し立てを行います。競売が申し立てられると、その情報は裁判所のウェブサイトに公開され、誰でも閲覧できる状態になります。
近隣住民に知られるリスクが高まり、プライバシーが守られなくなります。
滞納10〜12ヶ月目:競売開始決定
裁判所から「競売開始決定通知」が届きます。この通知が届くと、裁判所の執行官があなたの家を訪問し、現況調査を行います。家の中の写真が撮影され、その情報が競売物件として公開されます。
この段階でも、まだ任意売却という選択肢は残されています。しかし、時間は限られているため、すぐに専門家に相談する必要があります。
滞納12〜18ヶ月目:入札・開札
競売の入札が開始されます。入札期間は約1週間で、最も高い価格を入札した人が落札者となります。落札されると、あなたは家の所有権を失います。
競売での売却価格は、市場価格の50〜70%程度にしかならないことが多く、大幅に安い価格で家を失うことになります。
滞納18ヶ月以降:強制退去
落札者が代金を納付すると、所有権が落札者に移ります。落札者から立ち退きを求められ、応じない場合は強制執行により退去させられます。
引っ越し費用は一切もらえず、売却代金で住宅ローンを完済できなかった場合、多額の残債の返済義務が残ります。
2. 競売を避け「任意売却」を選ぶメリット
競売という最悪の事態を避けるために、「任意売却」という選択肢があります。任意売却とは、金融機関や保証会社の同意を得て、市場価格に近い金額で家を売却する方法です。
任意売却とは

任意売却は、住宅ローンの残債が家の売却価格を上回っている状態(オーバーローン)でも、債権者の同意を得ることで売却を可能にする手続きです。通常、オーバーローンの場合は抵当権を抹消できないため売却できませんが、任意売却では債権者が抵当権の抹消に同意してくれます。
あわせて読みたい
任意売却のメリット

任意売却には、競売と比較して多くのメリットがあります。
まず、売却価格が市場価格に近い金額(市場価格の80〜95%程度)になります。競売では市場価格の50〜70%程度にしかならないため、任意売却の方が圧倒的に高く売却できます。高く売却できれば、残債を大幅に減らすことができます。
次に、引っ越し費用を確保できる可能性があります。債権者との交渉により、売却代金から引っ越し費用(通常30〜100万円程度)を捻出してもらえる場合があります。競売では一切もらえないため、これは大きなメリットです。
また、プライバシーが守られます。任意売却は通常の不動産取引と同じように進められるため、競売のようにインターネット上に情報が公開されることはありません。近隣住民に知られるリスクを最小限に抑えられます。
さらに、売却時期を調整できます。債権者と協議の上、子供の学期末まで待ってもらったり、次の住まいが決まるまで猶予をもらったりすることが可能です。競売のように突然退去を迫られることはありません。
残債の返済計画も柔軟に設定できます。任意売却後に残債が残った場合でも、債権者と現実的な返済計画を協議できます。月々5,000円〜3万円程度の無理のない範囲で分割返済することが可能です。
あわせて読みたい
任意売却の注意点
任意売却にも注意点があります。債権者の同意が必要なため、必ずしも認められるわけではありません。また、競売の開札日までに売却を完了させる必要があるため、時間的制約があります。
任意売却を成功させるには、できるだけ早く専門家に相談することが重要です。競売開始決定通知が届いてからでは時間が限られてしまうため、滞納が始まった時点、または滞納しそうだと感じた時点で相談することをお勧めします。
あわせて読みたい
住宅ローンが払えなくても家に住み続ける3つの方法

病気で住宅ローンが払えない状況になっても、「今の家に住み続けたい」と願う方は多いでしょう。子供の学校や通院の都合、住み慣れた環境を離れたくないなど、様々な理由があります。
実は、住宅ローンが払えない状況でも、家に住み続ける方法が3つ存在します。ここでは、それぞれの方法について詳しく解説します。
1. リースバック(売却後に賃貸として住む)
リースバックとは、自宅を不動産会社や投資家に売却し、その買主と賃貸契約を結ぶことで引き続き住み続ける方法です。所有者ではなくなりますが、同じ家に住み続けられるため、生活環境を変えずに済みます。
リースバックの仕組み
リースバックは以下のような流れで進みます。まず、不動産会社や投資家に自宅を売却します。売却価格は市場価格の70〜90%程度になることが一般的です。売却代金で住宅ローンを返済します(オーバーローンの場合は、債権者の同意を得て任意売却と組み合わせます)。
次に、買主と賃貸借契約を結び、家賃を支払いながら同じ家に住み続けます。将来的に経済状況が改善したら、買い戻すことも可能です(買戻し特約を付けた場合)。
リースバックのメリット
リースバックのメリットとして、引っ越しが不要で、子供の転校や通院環境の変化を避けられます。近隣住民に家を売却したことを知られずに済みます。売却代金を一時的な生活費や治療費に充てることができます。固定資産税や修繕費などの維持費が不要になり、家賃のみの支払いになります。将来、経済状況が回復すれば買い戻せる可能性があります。
リースバックの注意点
一方、注意点もあります。売却価格に応じて家賃が決まるため、高く売ると家賃も高くなります。市場の賃料相場よりも高くなる場合があります。賃貸借契約の期間に制限がある場合があり、永久に住み続けられるとは限りません。オーバーローンの場合、債権者の承諾が得られないこともあります。買主が第三者に転売した場合、新しい所有者から立ち退きを求められるリスクがあります。
リースバックが向いているケース
リースバックは、一時的に収入が減っているが将来的に回復の見込みがある場合や、子供の学校や通院の都合で引っ越しを避けたい場合、近隣住民に知られたくない場合などに適しています。
リースバックを成功させるには、実績のある専門の不動産会社に相談することが重要です。ただし、中には悪質な業者もいるため、複数の業者に相談し、条件を比較検討しましょう。
2. 個人再生(住宅ローン特則を活用)
個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、3〜5年かけて返済していく債務整理の一種です。「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用すれば、持ち家を残しながら他の借金を減額できます。
個人再生の仕組み
個人再生では、住宅ローン以外の借金を最大8割カットできます。例えば、消費者金融からの借入500万円がある場合、これを100万円まで減額し、3年間で分割返済するといった形です。
住宅ローンは減額されませんが、返済計画を見直すことができます(リスケジュール)。他の借金が減額されることで、住宅ローンの返済を継続できるようになります。
個人再生のメリット
個人再生のメリットとして、自宅を残しながら経済的な再建を目指せることが最大のポイントです。住宅ローン以外の借金が大幅に減額され、月々の返済負担が軽減されます。給与差し押さえなどの強制執行を止めることができます。自己破産のように職業制限がないため、仕事を続けられます。
個人再生の条件と注意点
個人再生を利用するには、いくつかの条件があります。住宅ローン以外の借入がある場合にのみ利用可能です(住宅ローンだけの場合は利用できません)。安定した収入があり、減額後の借金を3〜5年で返済できる見込みが必要です。住宅ローンを滞納していないことが条件となります(滞納している場合は、まず滞納を解消する必要があります)。
注意点として、信用情報機関に事故情報が登録され(ブラックリスト)、5〜10年間は新たな借入やクレジットカードの作成ができなくなります。官報に氏名が掲載されます(ただし、一般の人が官報を見ることはほとんどありません)。弁護士費用や裁判所費用として、50〜80万円程度の費用がかかります(分割払いが可能な弁護士事務所もあります)。
個人再生が向いているケース
個人再生は、住宅ローン以外に消費者金融やカードローンなどの借金がある場合や、病気で一時的に収入が減ったが、将来的には回復する見込みがある場合、自己破産は避けたいが、借金の返済が困難な場合などに適しています。
個人再生は複雑な法的手続きが必要なため、必ず弁護士に相談しましょう。無料相談を実施している法律事務所も多いので、まずは相談してみることをお勧めします。
あわせて読みたい
3. 親族間売買(親族に買い取ってもらう)
親族間売買とは、親族(両親、兄弟姉妹、子供など)に自宅を買い取ってもらい、そのまま住み続ける方法です。「他人に家を売りたくない」「今の家に住み続けたい」という希望を叶えられる可能性があります。
親族間売買の仕組み
親族間売買では、まず親族に自宅を適正価格で買い取ってもらいます。適正価格とは、市場価格に近い金額のことで、著しく安い価格で売買すると贈与とみなされ課税される可能性があります。
親族が住宅ローンを組んで購入する場合もあれば、現金で購入する場合もあります。売却後、親族と賃貸借契約を結び、家賃を支払いながら住み続けます。または、将来的に買い戻す約束をして、一時的に所有権を移すという形も可能です。
親族間売買のメリット
親族間売買のメリットとして、住み慣れた家に住み続けられることや、将来的に買い戻せる可能性が高いこと、賃貸借契約の条件を柔軟に設定できること(家賃の金額や支払時期など)、第三者に売却するよりも安心感があることなどが挙げられます。
親族間売買の注意点
ただし、一般的な不動産取引とは異なり、以下の点に注意が必要です。
住宅ローン審査が厳しくなる傾向があります。親族間での売買は、融資した資金が住宅購入以外に流用されるリスクがあるため、金融機関が警戒します。そのため、通常の住宅ローンよりも審査が厳しく、融資を受けられない場合もあります。
安すぎる価格で売買すると、贈与とみなされ課税される可能性があります。適正価格での売買が重要で、不動産会社の査定書などを用意し、適正価格であることを証明する必要があります。
親族間でのトラブルが発生する可能性があります。金銭が絡むことで、これまで良好だった親族関係が悪化するリスクがあります。契約書をしっかりと作成し、お互いの権利義務を明確にしておくことが重要です。
親族間売買を成功させるポイント
親族間売買を成功させるには、不動産会社に査定を依頼し、適正価格を把握することが必要です。複数の不動産会社に査定を依頼し、平均的な価格を把握しましょう。契約書を専門家(弁護士や司法書士)に作成してもらい、法的に問題のない形で進めます。住宅ローンを取り扱っている金融機関に相談し、親族間売買でも融資可能か確認します(親族間売買に対応している金融機関は限られています)。
親族間売買は手続きが複雑になりやすいため、実績のある不動産会社や専門家に相談し、適切なサポートを受けましょう。
あわせて読みたい
病気による住宅ローン問題は、一人で悩まず専門家へご相談を

病気で住宅ローンが払えない状況は、誰にでも起こりうる問題です。しかし、一人で悩んでいても状況は改善しません。むしろ、時間が経過するほど選択肢は狭まり、問題は深刻化していきます。
ここでは、病気による住宅ローン問題の相談先と、それぞれの特徴について解説します。
1. 相談先ごとの特徴(金融機関・弁護士・任意売却専門家)
金融機関(住宅ローンを借りている銀行)
まず最初に相談すべきは、住宅ローンを借りている金融機関です。リスケジュール(返済計画の見直し)の相談ができ、一時的な返済額の減額や返済期間の延長などが可能な場合があります。滞納する前に相談することで、金融機関も柔軟に対応してくれる可能性が高まります。
ただし、金融機関は債権者の立場なので、あなたの味方とは限りません。あくまで「回収」を目的としているため、必ずしもあなたにとって最善の提案をしてくれるとは限りません。
弁護士・司法書士
法的な債務整理(個人再生、自己破産など)を検討する場合は、弁護士や司法書士に相談します。住宅ローン以外にも借金がある場合、個人再生で借金を減額できる可能性があります。法的な手続きを代行してくれるため、複雑な手続きを自分で行う必要がありません。
多くの法律事務所が無料相談を実施しているので、まずは相談してみることをお勧めします。ただし、弁護士費用がかかること(50〜80万円程度、分割払い可能な事務所もあります)や、債務整理をすると信用情報に傷がつくこと(ブラックリスト)には注意が必要です。
任意売却専門業者
家の売却を検討する場合、特にオーバーローンの場合は、任意売却専門の不動産会社に相談することが重要です。債権者との交渉を代行してくれ、市場価格に近い金額での売却を目指します。引っ越し費用の確保や、売却後の残債の返済計画についても相談できます。
当サイトを運営する一般社団法人 全国任意売却協会では、年間数百件の任意売却を成功させている実績があります。弁護士、司法書士、税理士などの専門家と連携した総合的なサポート体制を整えており、無料相談を実施しています。相談したからといって、必ずしも任意売却をしなければならないということはありません。
公的機関(社会福祉協議会、法テラスなど)
経済的に困窮している場合、公的機関に相談することも有効です。社会福祉協議会では、生活福祉資金貸付制度などの支援を受けられる場合があります。法テラスでは、経済的に余裕のない方に対して、無料で法律相談を受けられるサービスを提供しています。
これらの公的機関は、あなたの味方として親身に相談に乗ってくれます。まずは相談してみることをお勧めします。
2. まとめ:早めの行動が解決の鍵です
病気で住宅ローンが払えない状況になっても、放置すれば最終的に競売に至るリスクがあります。競売になると、市場価格よりも大幅に安く家を手放すことになり、多額の借金だけが残るという最悪の結果を招きます。
そうなる前に、保険や公的制度、リスケジュール、任意売却、個人再生といった取るべき手段を早めに検討しましょう。まずは、団信や就業不能保険、傷病手当金、労災保険、障害年金などが使えないかを確認します。
もしこれらの制度が使えない場合でも、金融機関へのリスケジュール相談、任意売却、リースバック、個人再生、親族間売買といった対処法があります。主な相談先は、金融機関、弁護士・司法書士、任意売却専門業者、公的機関などです。
早めの相談で、より多くの選択肢を残すことができます。滞納してから相談するよりも、滞納する前、または滞納しそうだと感じた時点で相談する方が、解決の選択肢は圧倒的に多くなります。
少しでも不安を感じたら、まずはお気軽にご相談ください。あなたの状況を丁寧にお聞きし、最適なご提案をいたします。一人で悩まず、専門家の力を借りて、この困難な状況を乗り越えましょう。
解決事例一覧
「ゆとりローン」の返済額倍増と教育費が直撃!計画的な任意売却で不安を乗り越えたケース
福岡市にお住まいのSさん(52歳)は、新築マンションを購入した際に「ゆとりローン」を利用しました。当初の月々返済額は11...
「住宅ローンを3人で組む」リスクが表面化。親子3人名義の家を任意売却したケース
Kさんは母と妹との3人家族で、夢だったマイホームを親子3人名義で購入。住宅ローンを3人で組む(収入合算)ことで審査を通し...
「旦那が借金を残して死んだら…」住宅ローンと不明な債務を相続放棄と任意売却で解決した事例
Tさんはご主人を病気で亡くされましたが、「旦那が借金を残して死んだらどうなるか」という不安通り、借金の有無も不明なまま働...
2軒分の住宅ローンと高額な債務を任意売却と自己破産でゼロに!再スタートを成功させたケース
Tさんは、新しい住宅を購入する際、以前所有していた戸建の残債に新築の住宅ローンを上乗せして融資を受け、2軒分のローンを抱...
50歳でうつ病を発症、「住宅ローンが払えない」状況から任意売却で再出発したケース
Bさんは群馬県高崎市で28年間勤務していましたが、50歳のときにうつ病を発症。1年後には早期退職となり、失業保険も切れた...
うつ病で働けず、住宅ローンがネックで生活保護も不可に。任意売却と自己破産で支援を確保したケース
Tさんは原因不明の体調不良からうつ病を発症し、経営していた会社を閉鎖。病気の悪化に加え、奥様が脳梗塞で半身不随となり、夫...
うつ病発症で住宅ローン返済困難に。退職と任意売却で負担を整理したケース
Kさんは愛知県あま市の戸建に一人で暮らしながら、鉄鋼関係の会社で課長職として勤務されていました。部下の金銭トラブルをきっ...