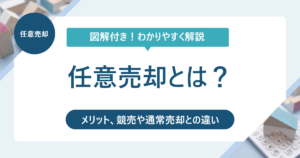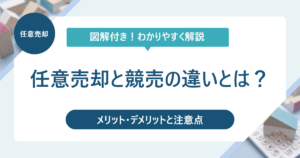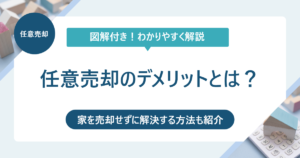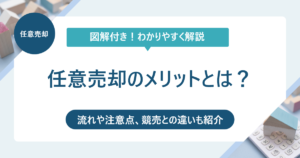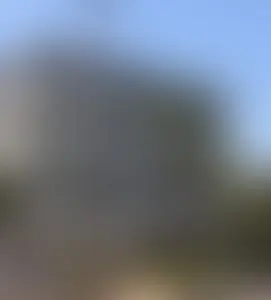競売の流れとは?回避するための方法も解説!
更新日 2025-10-30
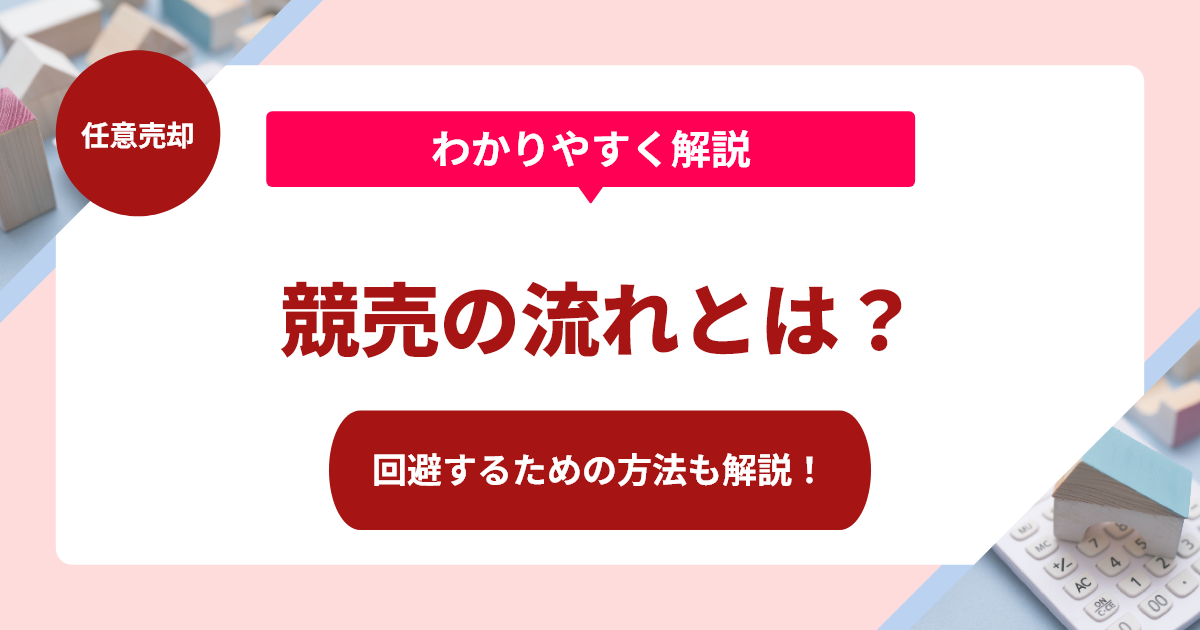

住宅ローンの返済が滞り、「このままだと競売になるのでは…」と不安を抱えていませんか?
本記事では、競売の流れを時系列で解説しつつ、競売を回避できる「任意売却」という選択肢についても紹介します。
まだ間に合うかもしれません。まずは正しい情報を知ることから始めましょう。
競売とは?その仕組みと種類
住宅ローンの返済が滞ると、「競売」という言葉が現実味を帯びてきます。競売とは、債務者がローンなどの返済をできなくなったときに、債権者の申立てにより裁判所が不動産を強制的に売却する手続きのことです。
ここでは、競売がどのような状況で始まり、どんな種類があるのかを見ていきましょう。
競売はどんな時に始まるのか
競売は、ローンの滞納が続いたときに突然やってくるものではありません。いくつかの段階を経て、最終的に裁判所が競売手続きに入る流れです。
一般的な競売までの流れ
- 金融機関からの支払い督促
- 「期限の利益喪失通知」により一括返済を求められる
- 保証会社による「代位弁済」
- 不動産の「差押え」
- 裁判所へ「競売開始申立て」
このように段階を追って手続きが進行し、債務者の同意がなくても競売は自動的に始まります。事前に対応しなければ、いつの間にか自宅が「差押え」状態になっていることもあるのです。
担保不動産競売と強制競売の違い
競売には大きく分けて「担保不動産競売」と「強制競売」の2つがあります。それぞれ、開始のきっかけや手続きの背景が異なります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 担保不動産競売 | 住宅ローンの担保にされた不動産が、ローン返済不能となった場合に売却される |
| 強制競売 | 税金滞納や損害賠償命令により、不動産が差押え・売却される |
どちらも「支払い不能」が原因ですが、担保の有無や申立人(債権者)が異なるのが特徴です。特に住宅ローン返済に関わるケースでは、多くが「担保不動産競売」に該当します。
参考:
住宅ローン滞納から競売開始までの流れ
住宅ローンの支払いが苦しくなり、数ヶ月にわたって滞納が続くと、いよいよ競売という言葉が現実味を帯びてきます。とはいえ、競売は突然始まるわけではなく、いくつかのステップを経て進行します。
ここでは、滞納から競売開始決定までの流れを時系列で整理しましょう。
滞納が続くと何が起きる?
最初の滞納から競売開始までには一定の猶予期間があります。この間に状況を改善したり、任意売却の準備を進めることも可能です。
| 滞納期間の目安 | 債権者(金融機関など)の対応内容 |
|---|---|
| 1〜2ヶ月 | 電話や郵送による督促。まだ柔軟な対応をしてくれることが多い |
| 3〜4ヶ月 | 「期限の利益喪失通知」により、一括返済を求められる段階 |
| 5ヶ月〜 | 保証会社に債権が譲渡され、対応がより厳格かつ機械的になる |
このように、時間が経つほど選択肢は狭まり、最終的には競売へと進んでいきます。3〜4ヶ月目までが、任意売却を選べる大きなチャンスです。
代位弁済と裁判所からの通知
「代位弁済(だいいべんさい)」とは、保証会社が債務者に代わってローンを一括返済する手続きのことです。
代位弁済が行われると、ローンの債権者は金融機関から保証会社へと変わります。以降の対応は、より事務的で厳格になり、個別の事情が考慮されにくくなります。
さらにその後、保証会社が裁判所へ競売の申立てを行うと、債務者の元に「競売開始決定通知」が届きます。この通知は、裁判所から公式に「競売を始めます」と伝えられるもので、非常に大きな精神的インパクトを与える局面です。
しかし、この時点でもまだ任意売却によって競売を止められる可能性があります。通知が届いたらすぐに専門家に相談することが、状況を好転させる鍵になるでしょう。
差押・競売開始決定通知の意味
競売手続きが始まると、自宅は「差押え」の状態になります。「差押え」は、所有者の自由に売却したり動かしたりできない状態を意味し、法務局にもその情報が登記されます。
そして、裁判所から届く「競売開始決定通知」は、手続きが本格的に進行することを知らせる重要な文書です。この通知を受け取ると、不安や動揺が大きくなるかもしれませんが、まだ希望は残されています。
実は、競売の「開札日の2日前」までであれば、任意売却によって競売を取り下げることが可能な場合があります。諦める前に、早めの行動が重要です。
参考
競売手続きのステップ
競売は、ただ「家が売られる」だけの単純な仕組みではありません。裁判所主導のもと、調査・情報公開・入札・売却といった一連の手続きが、法律に基づいて進行します。
ここでは、競売の手続きの全体像を順を追って解説します。
現況調査と評価書の作成
競売の準備段階としてまず行われるのが、「現況調査」や「評価書」の作成です。資料は、購入希望者が入札の判断をするために重要な情報となります。
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| 現況調査報告書 | 裁判所の執行官が現地に訪問し、建物や敷地の状況を確認する調査 |
| 評価書 | 不動産鑑定士が市場価格をもとに物件価値を査定する文書 |
| 物件明細書 | 抵当権や所有権の状況、法的トラブルの有無などを記載した概要書類 |
上記3つの資料は「3点セット」と呼ばれ、入札希望者に公開されます。記載された内容によっては、入札価格や購入の判断に大きく影響するため、債務者にとっても非常に重要な手続きです。
BITサイトでの情報公開と入札手続き
現況調査と評価が完了すると、物件情報は裁判所が運営する公式サイト「BIT(不動産競売物件情報サイト)」に掲載されます。誰でも無料で閲覧できる仕組みで、競売の物件情報は全国に公開されます。
BITでは、物件の写真や3点セットの内容、最低入札価格などが確認できます。投資家や個人が自由に物件を選び、入札に参加することが可能です。
入札に参加するには、買受申出保証金(通常、基準価格の20%程度)を裁判所に納めたうえで、封筒に金額を記入して提出します。競売は一発勝負の入札制となっており、提出後の変更やキャンセルはできません。
開札〜売却許可・代金納付・明渡し
入札が終わると、いよいよ「開札(かいさつ)」が行われます。これは、各入札者の封筒を開け、最も高額で入札した人を決定する手続きです。
その後は以下のような流れで売却が成立していきます。
開札後の手続きの流れ
- 開札日:裁判所で入札価格を開封し、最高額の入札者を決定
- 売却許可決定:裁判所が問題なしと判断すれば正式に売却が認められる
- 代金納付期限の通知:落札者は指定された期限までに残代金を支払う
- 所有権移転登記:代金支払い完了後、落札者の名義で登記が行われる
- 明渡命令・強制執行:元の所有者が退去しない場合は裁判所が立退きを命令し、強制執行が行われることも
一連の流れは、スムーズに進んだとしても約1年〜1年半の期間を要します。途中でトラブルが起きたり、債務者が対応を怠った場合、さらなる時間や費用が発生する可能性もあるでしょう。
参考
競売になったらどうなる?生活への影響
競売によって家が売却されたあと、もっとも気になるのが「その後の生活はどうなるのか」という点でしょう。実際には、退去のタイミングや、残った住宅ローンの処理など、まだまだ重要な問題が残ります。
ここでは、競売後の現実について探っていきましょう。
立ち退きはいつ?強制執行の現実
落札者が代金を納付し、所有権が移転すると、裁判所は「引渡命令」を発令します。もともと住んでいた債務者には、速やかな退去が求められます。
しかし、自主的に退去しない場合は、次のような流れで「強制執行」が行われることになります。
- 執行官が自宅を訪問し、明渡しの準備を進める
- 警察が同行することもあり、トラブルが起きた場合にはその場で対応
- 家具や家電などの家財道具は搬出され、鍵は交換される
- ご近所に知られる可能性もあり、家族への精神的な負担も大きい
強制執行は精神的にも非常に大きなストレスとなります。できる限りその前に、任意での退去や交渉を行うことが望ましいでしょう。
残ったローンはどうなるのか
競売で自宅が売却されたとしても、その金額がローンの残額に満たないケースは非常に多く見られます。この差額分(残債務)は、競売後も債務者に対して支払い義務が残ります。
例えば、ローン残高が2,500万円、競売での売却額が1,800万円だった場合、700万円程度の借金が引き続き請求されます。この残債については、任意整理や自己破産などの法的な債務整理を検討することも必要です。
放置してしまうと、給与や預貯金の差押えなど、さらなる生活への影響が続く恐れがあります。競売後こそ、生活再建のために専門家への相談が大切です。
参考
競売を回避できる「任意売却」という選択
競売の進行が迫る中でも、実はまだ選べる道があります。
それが「任意売却」です。
任意売却とは、債権者と合意のうえで不動産を売却し、競売を避ける方法です。強制的に進む競売とは異なり、ある程度自身の意思や条件を反映できるのが大きな特徴です。
任意売却の流れとメリット
任意売却は、競売のようにすべてが裁判所主導で決まるのではなく、債務者と債権者が協議して進める売却方法です。信頼できる専門機関や不動産会社を通じて、以下のようなメリットが得られる可能性があります。
任意売却の主なメリット
- 市場価格に近い金額で売却でき、競売より高く売れる傾向がある
- 残ったローン(残債)をより少なくできる可能性がある
- 引越費用や生活資金を確保できる場合もある
- 近所に知られにくく、家族のプライバシーも守られやすい
- 通常の不動産売買と同じ流れで進むため、負担が少ない
このように、任意売却は精神的・経済的な負担を軽減できる現実的な選択肢です。早めに行動すればするほど、交渉の余地や選択肢も広がります。
どの段階まで任意売却は可能か
「もう競売の通知が来てしまったから無理では…?」と不安に思う方もいるかもしれません。ですが、任意売却は競売開始決定通知が届いたあとでも可能です。
具体的には、開札日の2日前までであれば、任意売却により競売を取り下げられる可能性があります。
ただし、実際には以下のような段取りが必要です。
- 債権者(保証会社など)との同意
- 売却価格の査定と買主の確保
- 必要書類の準備と手続きの調整
上記すべて短期間で進める必要があるため、早ければ早いほど成功の確率が高まります。不安を感じた時点で、無料相談などを利用して専門家に状況を共有することが、間に合うかどうかの大きな分かれ道になるでしょう。
参考
気軽に任意売却の無料相談を

競売開始決定通知が届いたとしても、まだ任意売却で競売を止められる可能性があります。
そのチャンスを活かすためには、早めの行動と信頼できる専門機関への相談が何より重要です。
「任意売却ほっとなび」は、任意売却に特化した全国対応の支援団体で、弁護士・不動産会社・金融機関と連携し、自己資金がない場合でも状況に応じた対応が可能です。相談は匿名・無料・オンラインでも受け付けており、難しい専門用語がわからなくても丁寧にサポートいたします。
「まだ間に合うかもしれない」と思ったその瞬間が、未来を変えるチャンスです。
まずは気軽に、ご自身の状況を話してみることから始めてみませんか?
このページで出てきた専門用語
用語一覧へ解決事例一覧
2軒分住宅ローン負担増、任意売却と自己破産でゼロ負担に再出発したケース
Tさんは、新しい住宅を購入する際、以前所有していた戸建の残債に新築の住宅ローンを上乗せして融資を受け、2軒分のローンを抱...
「ゆとりローン」の落とし穴。定年後に膨らんだ返済負担から任意売却で脱出したケース
Tさんは40代で新築マンションを購入。当時主流だった「ゆとりローン」を利用し、当初は金利のみの支払いで月々の負担も少なく...
「ゆとりローン」の返済額倍増と教育費が直撃!計画的な任意売却で不安を乗り越えたケース
福岡市にお住まいのSさん(52歳)は、新築マンションを購入した際に「ゆとりローン」を利用しました。当初の月々返済額は11...
「住宅ローンを3人で組む」リスクが表面化。親子3人名義の家を任意売却したケース
Kさんは母と妹との3人家族で、夢だったマイホームを親子3人名義で購入。住宅ローンを3人で組む(収入合算)ことで審査を通し...
「旦那が借金を残して死んだら…」住宅ローンと不明な債務を相続放棄と任意売却で解決した事例
Tさんはご主人を病気で亡くされましたが、「旦那が借金を残して死んだらどうなるか」という不安通り、借金の有無も不明なまま働...
40代で会社が倒産、過労と離婚を経て任意売却で生活を立て直したケース
Dさんは東京都清瀬市で不動産関連会社を経営していましたが、業績悪化により会社は倒産。借金こそなかったものの、その直後に過...
2軒分の住宅ローンと高額な債務を任意売却と自己破産でゼロに!再スタートを成功させたケース
Tさんは、新しい住宅を購入する際、以前所有していた戸建の残債に新築の住宅ローンを上乗せして融資を受け、2軒分のローンを抱...