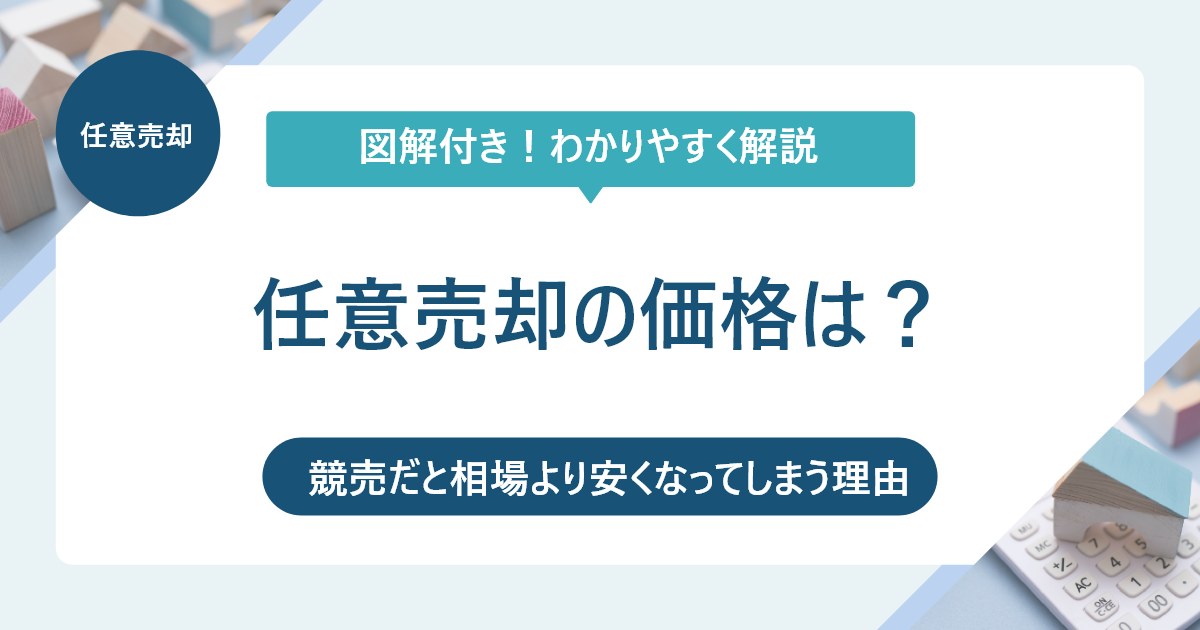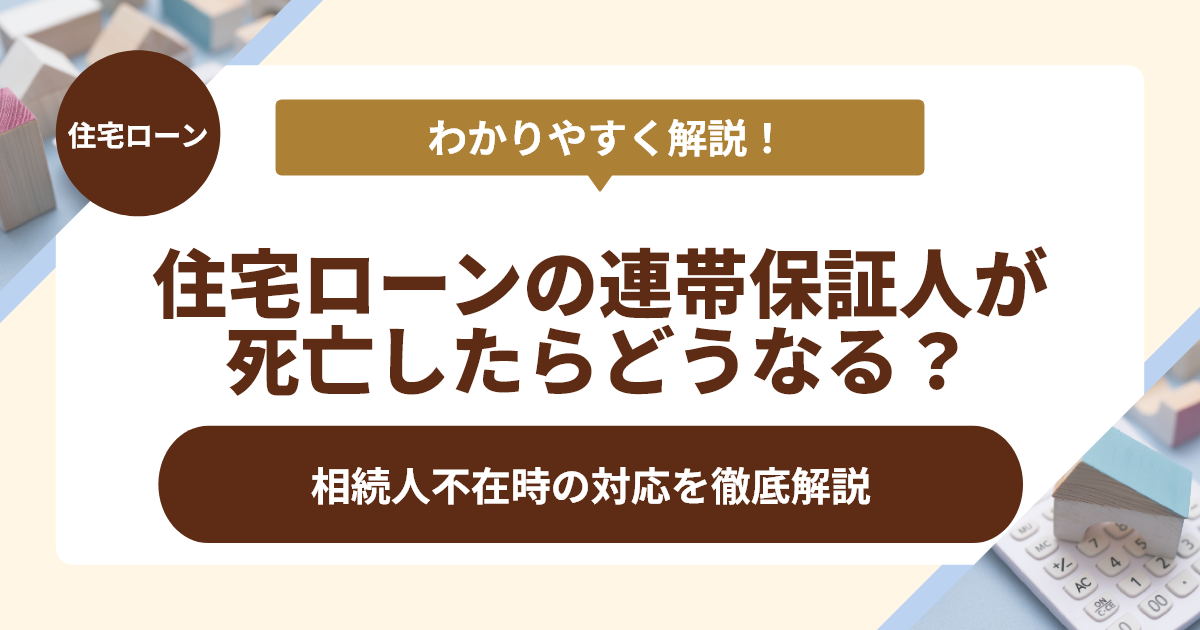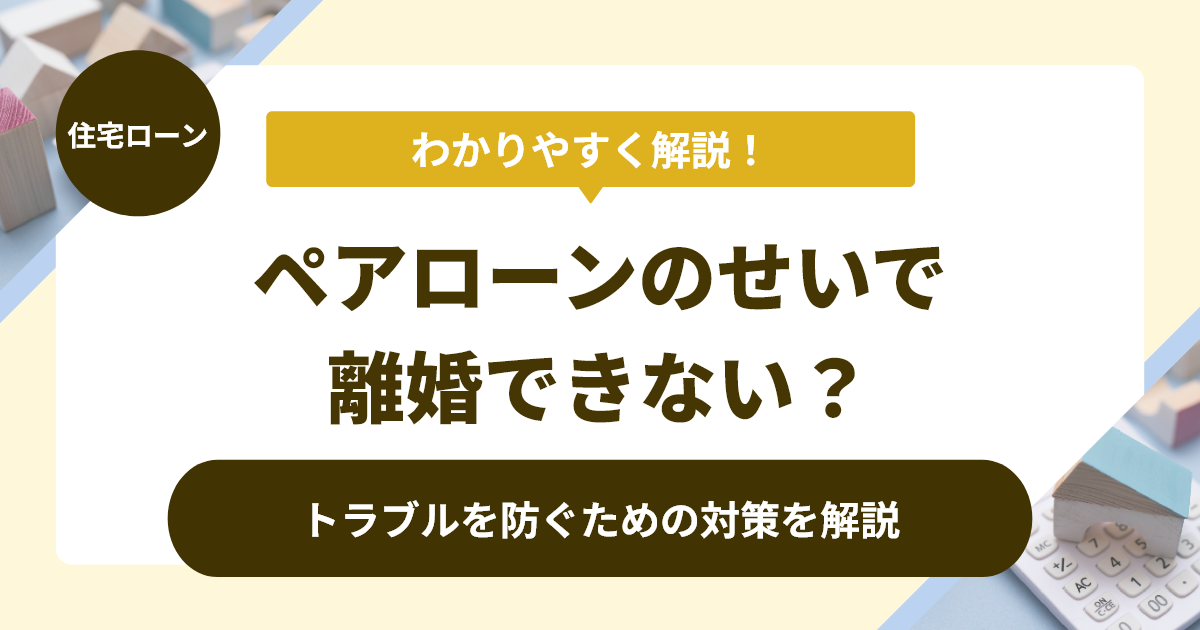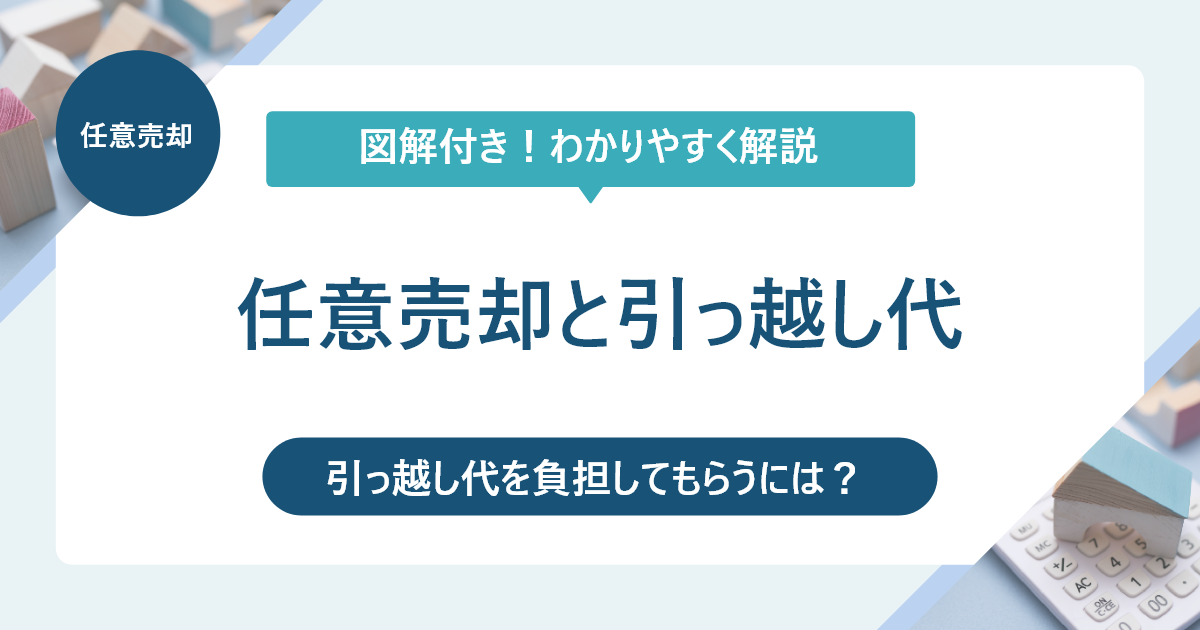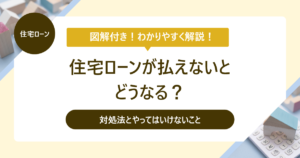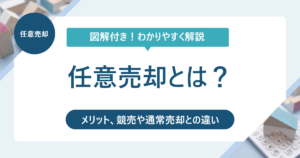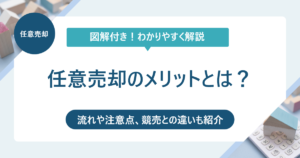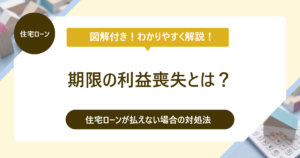住宅ローンあるけど離婚したい!解決策と対処法を解説
更新日 2025-11-24
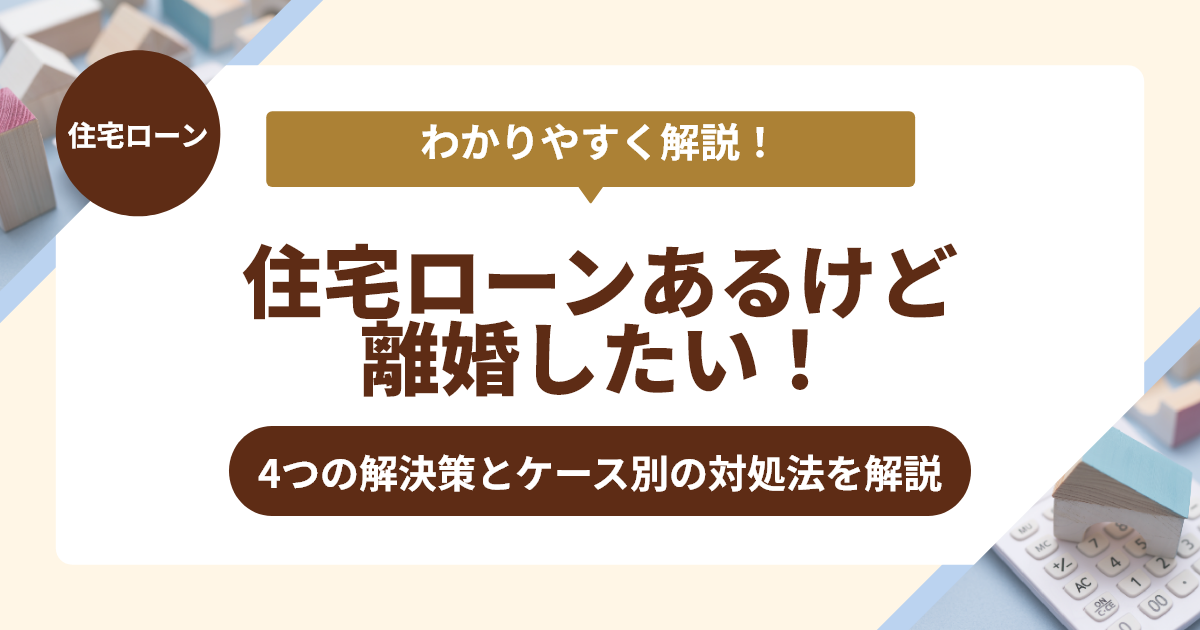

「夫と離婚したいが、住宅ローンが何十年も残っている」
「ペアローンを組んでいる場合、家はどう処理するのが正解?」
離婚を考えたとき、最大の足かせとなるのが「持ち家」と「住宅ローン」の問題です。
結論から申し上げますと、住宅ローンが残っていても離婚は可能ですが、家の処分を後回しにして離婚届を出すのは絶対に避けてください。
「とりあえず夫が住んで払い続ける」といった安易な口約束で離婚したがために、数年後に自宅が競売にかけられたり、元妻の給与が差し押さえられたりするケースが後を絶たないからです。
この記事では、住宅ローンがある状態で離婚するための「4つの選択肢」と、泥沼のトラブルを避けるための「連帯保証人の外し方・注意点」について、専門家が徹底解説します。
1. 住宅ローンがあるけど離婚したい!4つの選択肢

離婚時にマイホームをどうするかは、大きく分けて以下の4つのパターンがあります。
現在の経済状況や、お子様の学校などの事情に合わせて検討しましょう。
| 選択肢 | メリット | デメリット・リスク |
|---|---|---|
| ① 家を売却して完済 (最も推奨) |
後腐れなく関係を清算できる。 将来のトラブルリスクがゼロ。 |
オーバーローンの場合、 差額を現金で用意する必要がある。 |
| ② 夫が住み、夫が払う | 夫の生活環境が変わらない。 手続きが比較的簡単。 |
連帯保証人の場合、夫が滞納すると 元妻に請求がいく。 |
| ③ 妻が住み、夫が払う | 子供の転校などを避けられる。 | 夫が支払いを止めると競売になる。 銀行の契約違反になるリスクあり。 |
| ④ 妻が住み、妻が払う | 自分の資産として守れる。 夫との金銭関係が切れる。 |
妻単独でローンの借り換え審査に 通る必要がある(ハードル高)。 |
選択肢①:家を売却して住宅ローンを完済する
最もトラブルが少なく、理想的なのがこの方法です。
家を売ってローンを全額返し、手元に残ったお金(売却益)を夫婦で財産分与します。
ただし、家の価値よりもローン残高の方が多い「オーバーローン」の場合は、売却時に不足分を現金で用意しなければなりません。
現金が用意できない場合は、後述する「任意売却」を検討する必要があります。
あわせて読みたい
選択肢②:夫が住み続け、夫がローンを払う
名義人である夫がそのまま住むケースです。
一見問題なさそうですが、妻が「連帯保証人」になっている場合は要注意です。離婚しても連帯保証人は外れないため、将来夫が再婚などで支払いを滞納した場合、突然、元妻に一括請求が来ます。
選択肢③:妻が住み続け、夫がローンを払う
「養育費の代わり」として選ばれることが多いパターンですが、最もリスクが高い選択肢です。
- 勝手に売却されるリスク:名義人は夫なので、妻に無断で家を売却される可能性があります。
- 滞納・競売のリスク:夫の支払いが止まれば、妻と子供は強制退去になります。
- 銀行の契約違反:住宅ローンは「名義人が住むこと」が条件です。夫が出て行ったことが銀行にバレると、一括返済を求められる恐れがあります。
選択肢④:妻が家を買い取る(借り換え)
妻が自分の名義で住宅ローンを組み直し、夫から家を買い取る形です。
夫との縁を完全に切ることができますが、妻自身に「夫のローン残高全額」を借りられるだけの年収と信用情報(正社員勤続年数など)が必要となり、ハードルは高めです。
2. 離婚時に絶対確認すべき「3つの危険ポイント」

離婚届に判を押す前に、必ず以下の3点を確認してください。
これを確認せずに離婚すると、数年後に「こんなはずじゃなかった」と後悔することになります。
① オーバーローンになっていないか?
まず、「家がいくらで売れるか(査定額)」と「ローン残高」を比較してください。
- アンダーローン(査定額 > ローン残高):売ればプラスになる状態。財産分与の対象です。
- オーバーローン(査定額 < ローン残高):売っても借金が残る状態。マイナスの財産となり、揉める原因になります。
オーバーローンの場合、通常の不動産売却はできません。この問題を解決できるのが「任意売却」です。
② 妻が「連帯保証人」になっていないか?
契約書を確認してください。「連帯保証人」や「連帯債務者(ペアローン)」になっている場合、離婚してもその責任は絶対に消えません。
銀行は「離婚したから」という理由では、連帯保証人の解除を認めてくれません。外れるには「代わりの保証人を立てる」か「ローンを完済する」しかありません。
③ ペアローンの解消はできるか?
夫婦それぞれがローンを組んでいる「ペアローン」の場合、一本化するには「夫が妻の分まで借り換える(またはその逆)」必要があります。
相手に十分な返済能力がない場合、一本化はできず、離婚後も元配偶者のローンに関わり続けることになります。
あわせて読みたい
3. ローンが残る家を売るための手順
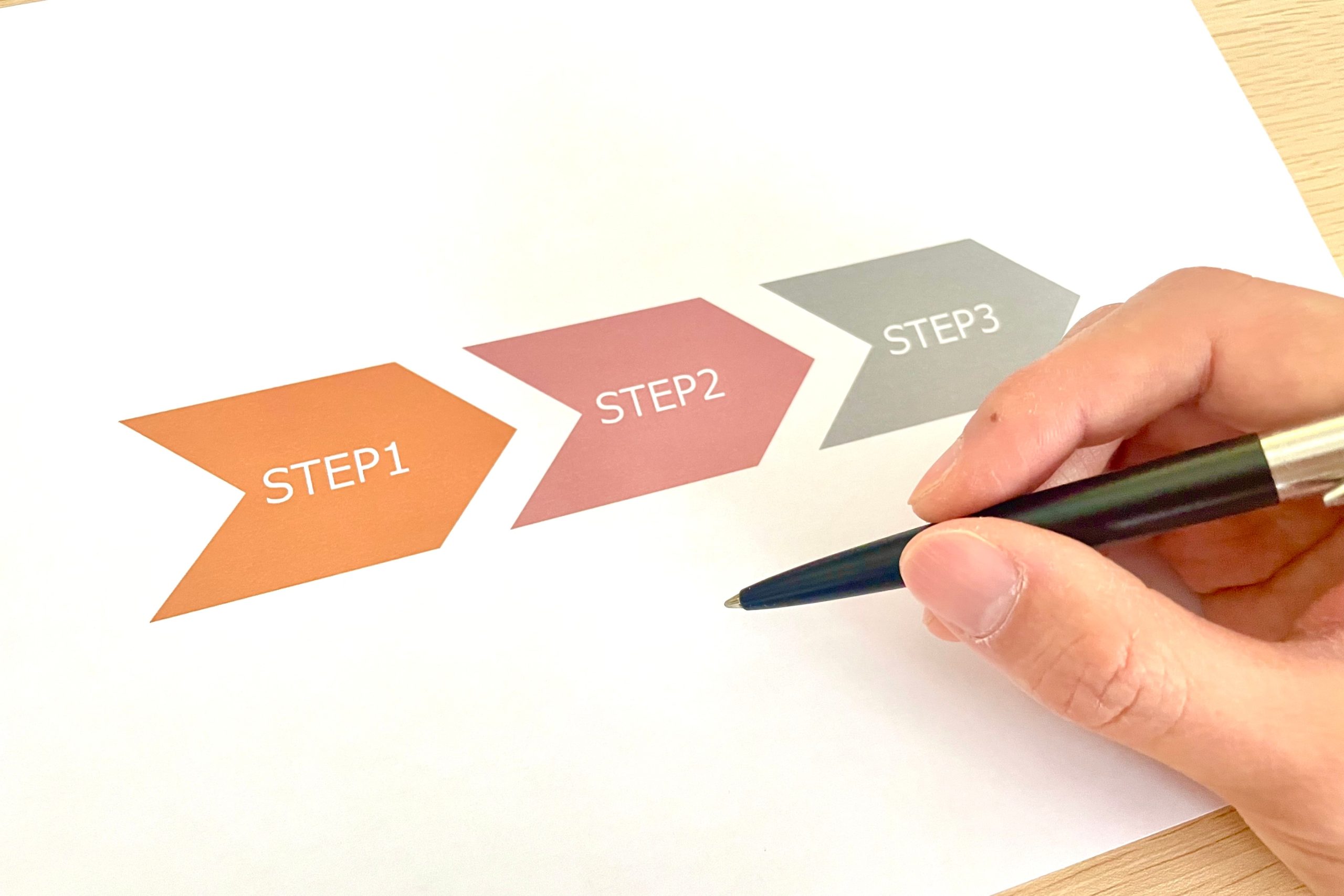
トラブルを避けるために最も確実な「売却」の手順を解説します。
STEP1:名義と残債の確認
まずは現状把握です。金融機関から届く残高証明書などで「ローン残高」を確認し、法務局で「登記事項証明書」を取得して名義人を確認します。
STEP2:家の査定(オーバーローンの確認)
不動産会社に査定を依頼し、今の家がいくらで売れるかを確認します。
この時点で「売却額 < ローン残高」であることが分かった場合、通常の不動産会社では「売れません(現金を用意してください)」と断られることがあります。
その場合は、私たちのような「任意売却の専門機関」にご相談ください。
STEP3:売却方法の決定

- アンダーローンの場合:一般仲介で高く売れるのを待ちます。売却益を財産分与します。
- オーバーローンの場合:「任意売却」を選択します。債権者と交渉し、借金が残る状態でも売却を成立させます。
STEP4:離婚届の提出
家の売却方針が決まり、決済の目処が立ってから離婚届を提出するのがベストです。
離婚後に相手と連絡が取れなくなると、売却の同意が得られず、家が「塩漬け」状態になり、最終的に競売になってしまうリスクがあるからです。
4. 「売りたいけど借金が残る」なら任意売却

離婚したいけれど、家を売ってもローンが完済できないため、身動きが取れない…。
そんな方のための救済措置が「任意売却(にんにばいきゃく)」です。
任意売却には以下のメリットがあります。
- オーバーローンでも売却可能:銀行の合意を得て、借金を残したまま抵当権を解除できます。
- 連帯保証人問題の解決:家を売却することで、連帯保証人のリスクを(全額ではないものの)大幅に軽減、あるいは解消できる可能性があります。
- 引越し費用の確保:売却代金から引越し費用を控除してもらえる可能性があり、離婚後の新生活資金に充てられます。
あわせて読みたい
あわせて読みたい
5. 離婚と住宅ローンの解決事例

事例:別居後に夫が音信不通に…競売寸前で解決
離婚協議中に別居し、夫が家に残りましたが、その後夫がローンを滞納して行方不明に。連帯保証人である妻の元に、銀行から一括請求が届きました。
当協会が夫の所在を調査して連絡を取り、任意売却への協力を取り付けました。結果、家は市場価格で売却でき、残債も無理のない分割払いとなり、妻は破産を免れました。
離婚前に「家の結末」を決めておきましょう

住宅ローン問題を先送りにしたまま離婚するのは、時限爆弾を抱えて生きていくようなものです。
相手と連絡が取れる今のうちに、家の処分方法を決めておくことが、あなた自身の未来を守ることに繋がります。
「オーバーローンで売れないかもしれない」
「連帯保証人を外れたい」
「夫と顔を合わせずに手続きを進めたい」
このようなお悩みをお持ちの方は、一般社団法人 全国任意売却協会にご相談ください。
弁護士とも連携し、離婚に伴う不動産売却や残債の処理について、あなたの利益を第一に考えた解決策をご提案します。
解決事例一覧
「ゆとりローン」の落とし穴。定年後に膨らんだ返済負担から任意売却で脱出したケース
Tさんは40代で新築マンションを購入。当時主流だった「ゆとりローン」を利用し、当初は金利のみの支払いで月々の負担も少なく...
2軒分住宅ローン負担増、任意売却と自己破産でゼロ負担に再出発したケース
Tさんは、新しい住宅を購入する際、以前所有していた戸建の残債に新築の住宅ローンを上乗せして融資を受け、2軒分のローンを抱...
40代で会社が倒産、過労と離婚を経て任意売却で生活を立て直したケース
Dさんは東京都清瀬市で不動産関連会社を経営していましたが、業績悪化により会社は倒産。借金こそなかったものの、その直後に過...