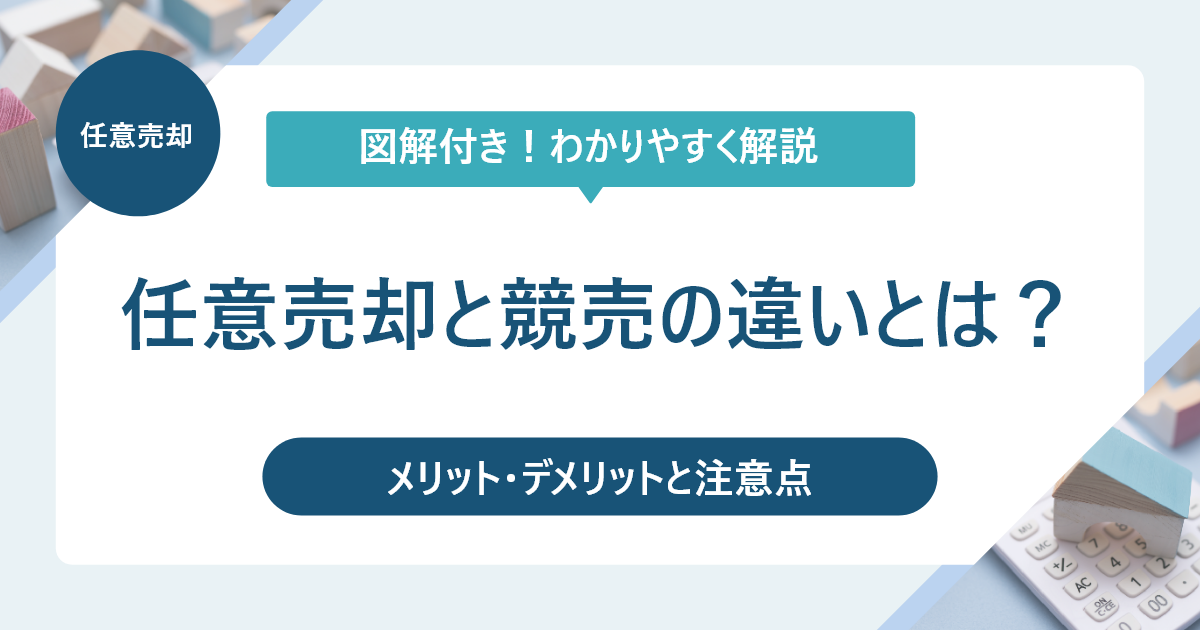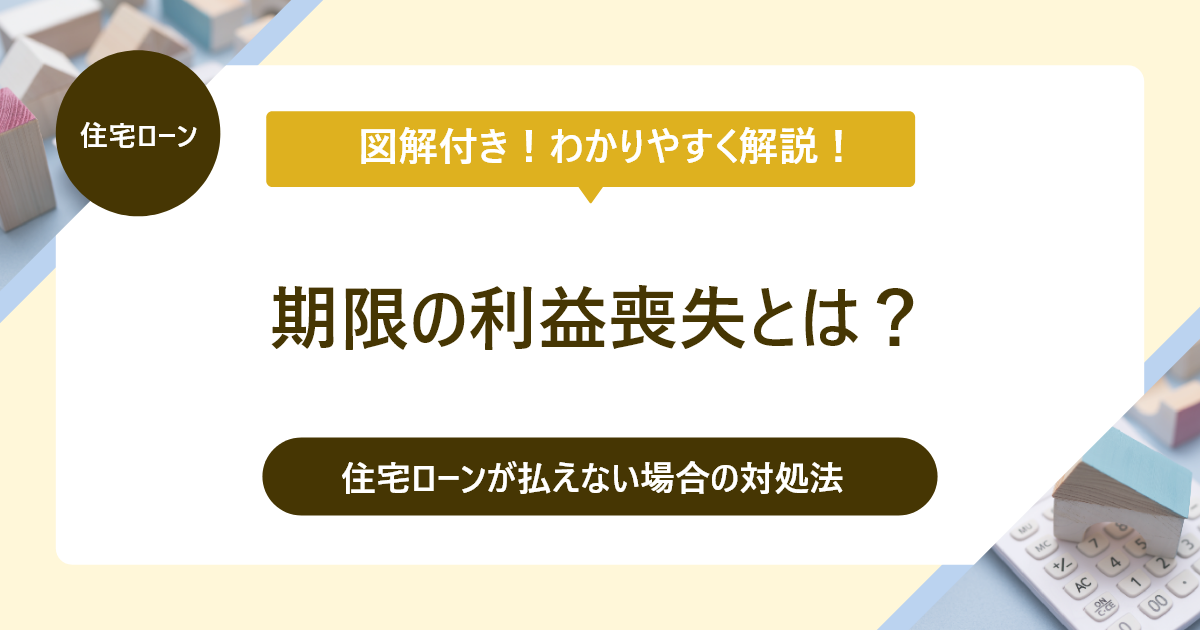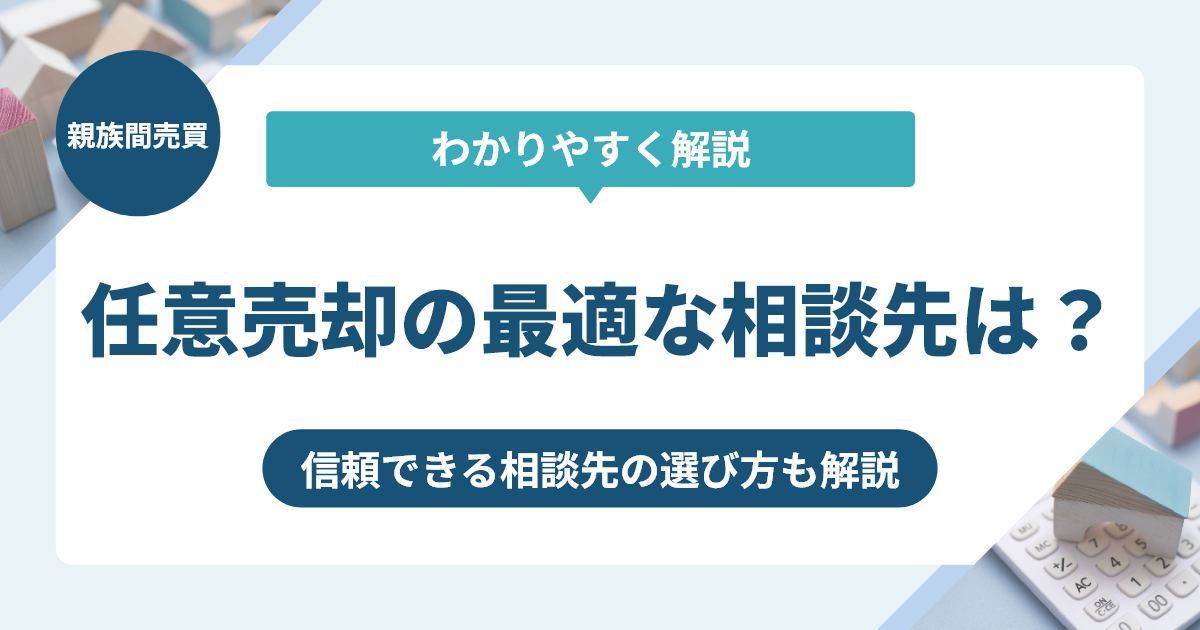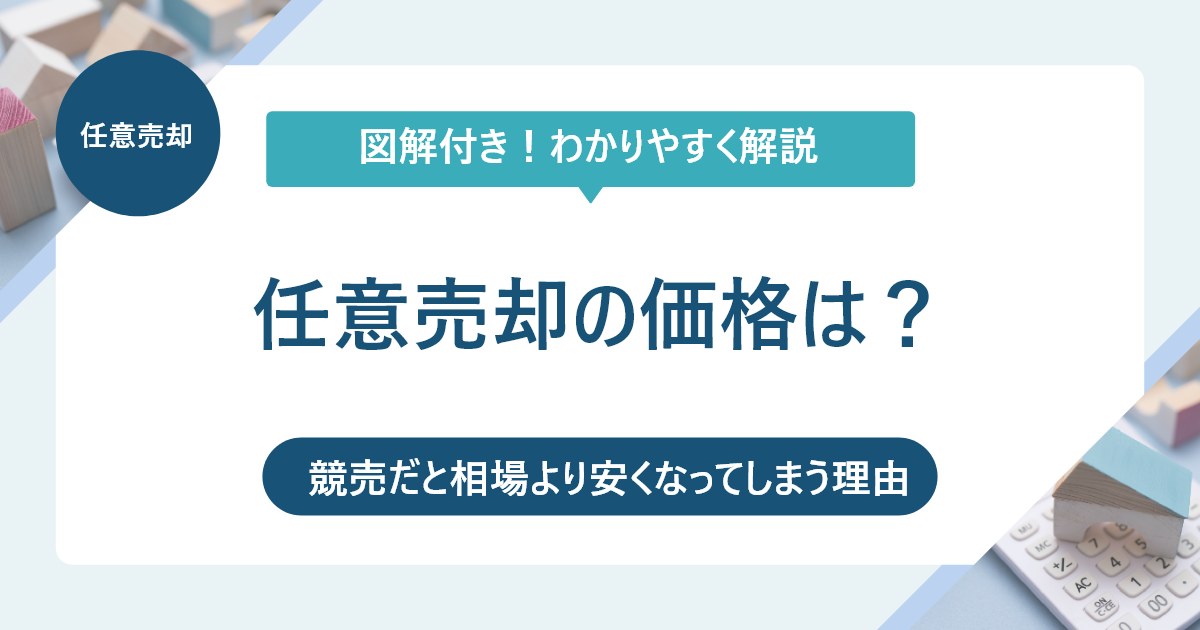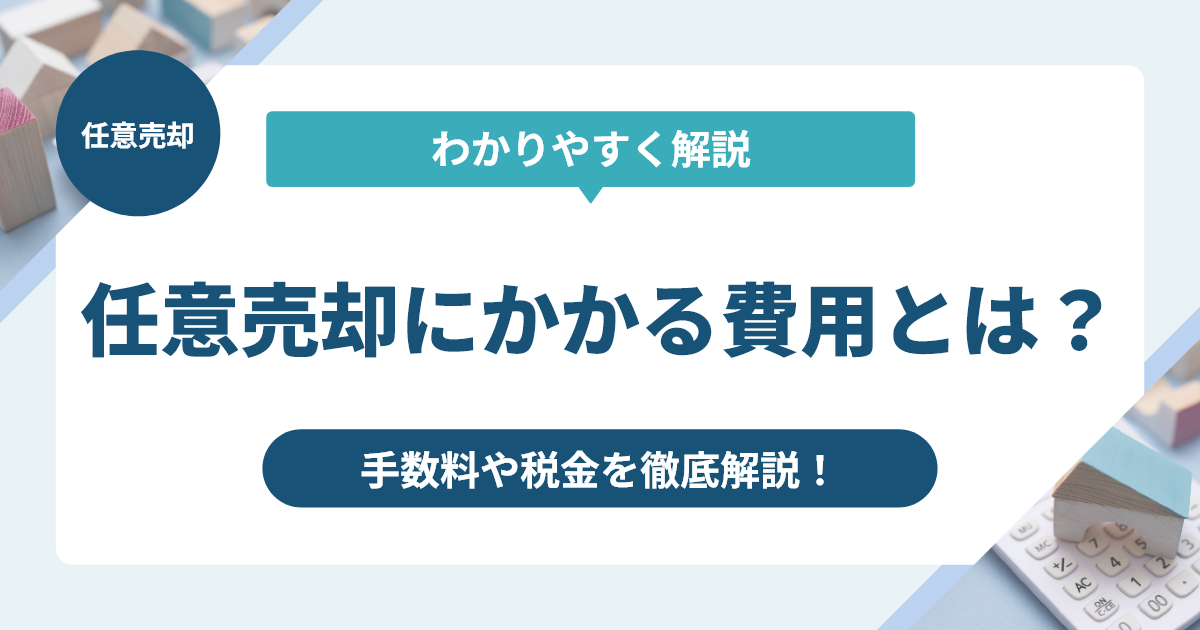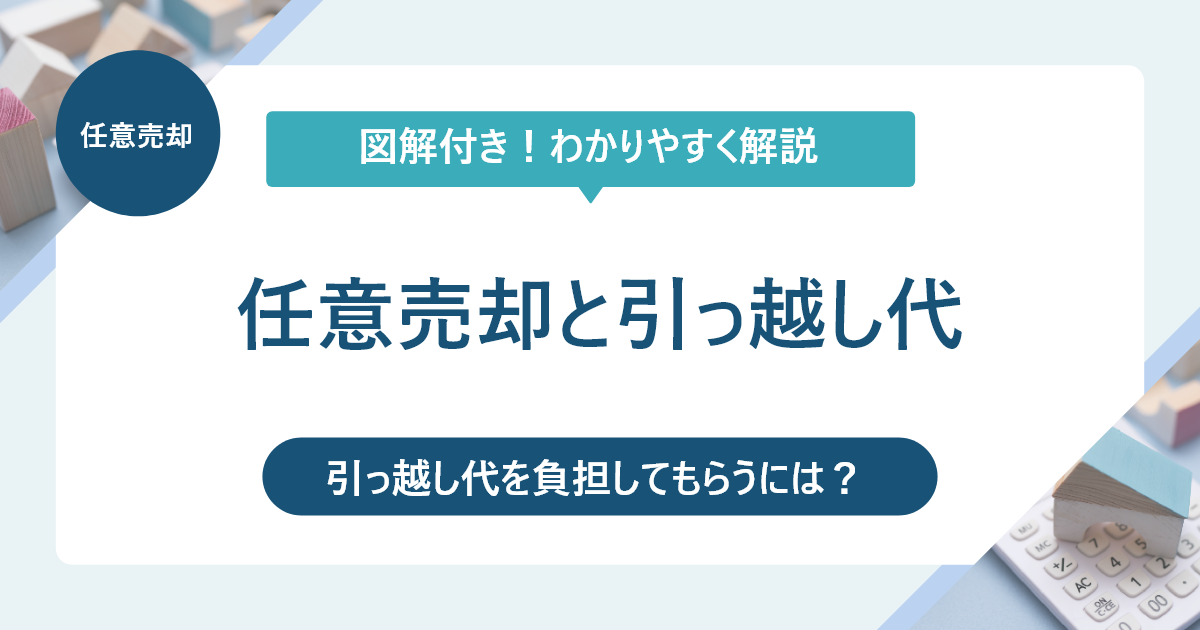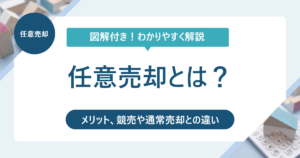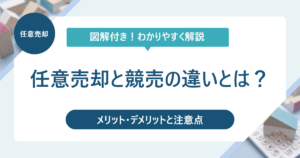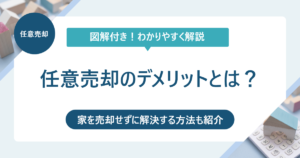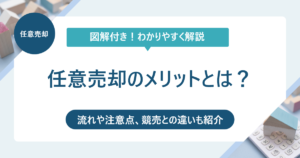任意売却の条件とは?必要な準備と流れ、成功させる方法を解説
更新日 2025-10-20
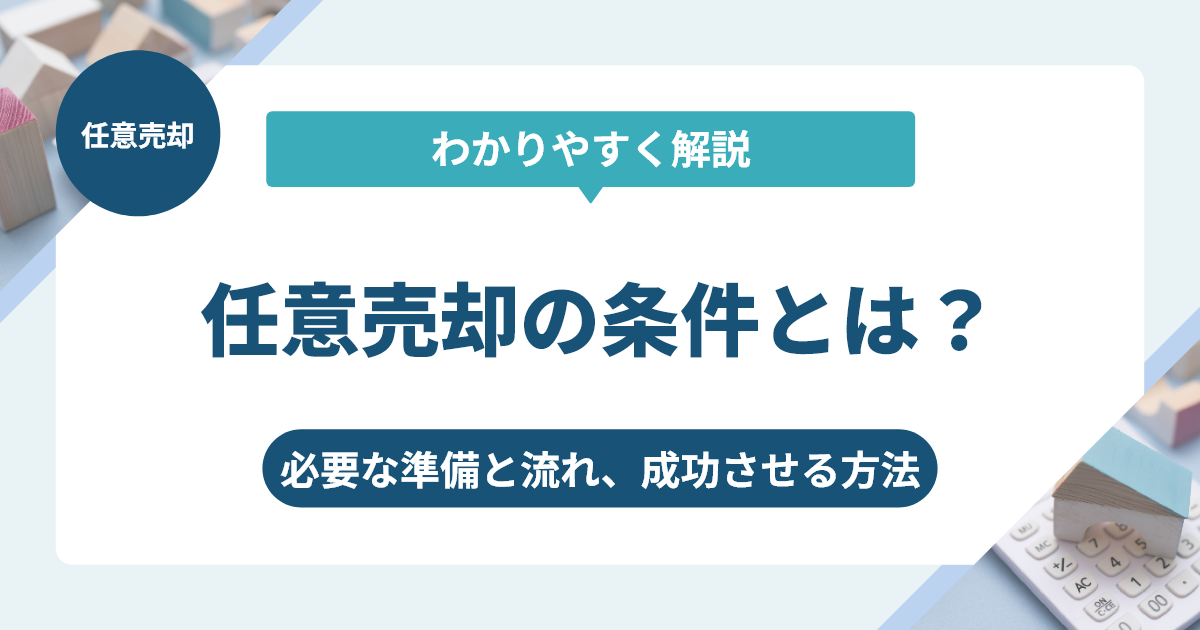

任意売却を検討している方の中には「どんな条件があるの?」「任意売却は誰でもできるの?」といった疑問を持っている方もいるでしょう。
任意売却を行うと、競売を回避できる上に、より有利な条件で自宅を売却できます。
また、住宅ローンを滞納したことを知人や友人に知られるリスクを軽減可能です。
ただし、任意売却は金融機関の同意が必要なため、必ず実現できるわけではありません。
本記事では、任意売却の条件や手続きの流れについて解説します。
住宅ローン危険度診断


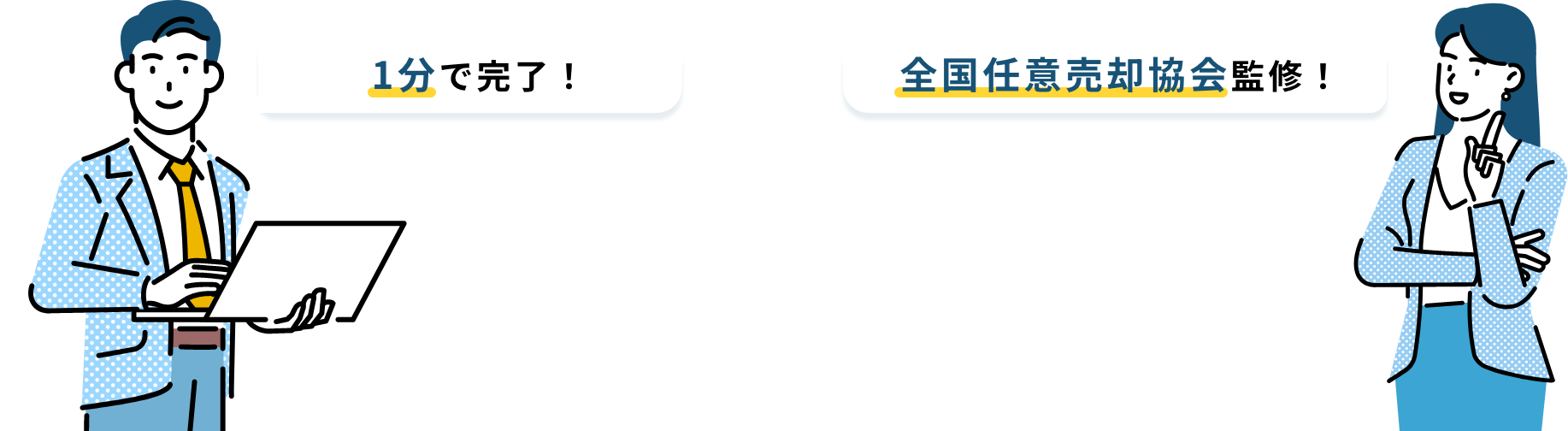
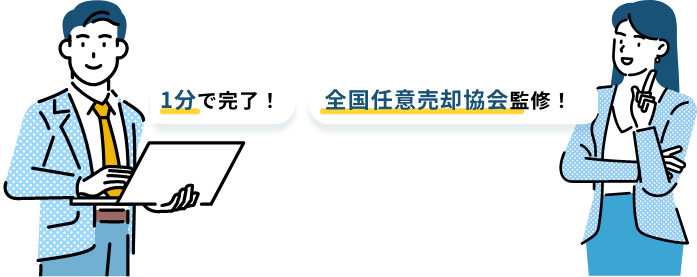
任意売却に必要な条件

任意売却は、誰でもできるわけではありません。
手続きを進めるには、債権者の同意を得るなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
事前に条件を確認して、自分が該当するかチェックしておきましょう。
債権者の同意が得られている
任意売却を進めるには、債権者である金融機関の同意が必要です。
なぜなら、自宅の売却代金が住宅ローン残債を下回る「オーバーローン」の状態であり、抵当権も外せないためです。
売却代金がローン残債を上回る「アンダーローン」の状態であれば、ローンを完済できるため、金融機関の同意は必要ありません。
債権者との交渉が難しいケースも多いですが、同意を得ることで任意売却を進めることができます。
共有名義人の同意がある

自宅が共有名義の場合、任意売却を進めるには共有名義人全員の同意が必要です。
例えば、親族から資金援助を受けた際に共有持分を設定している場合は、親族にも所有権があるため、任意売却の同意を得る必要があります。
共有名義人の同意を得ずに、自分だけの判断で進めることはできないことに注意しましょう。
連帯保証人の同意がある
任意売却を進めるには、連帯保証人の同意が必要です。
連帯保証人は、任意売却後に住宅ローンが残った場合、契約者とともに返済義務を負うことになります。
そのため、事前に相談して了承を得る必要があります。
連帯保証人が元配偶者やその親族の場合は、関係性の問題から、話し合いがスムーズに進まないこともあるため注意が必要です。
話し合いが難しい場合には、専門業者などにアドバイスをもらうとよいでしょう。
あわせて読みたい
修繕積立金や管理費の滞納がない
自宅がマンションの場合、修繕積立金や管理費に滞納があると承認が難しくなることがあります。
修繕積立金や管理費の滞納がある場合は、引き渡しまでに支払う必要があります。
滞納額が少なければ売却代金から充当できる場合もあります。
しかし、金額が大きいと金融機関の受け取る金額が減ることから、任意売却の承認が難しくなることもあるため注意が必要です。
滞納がある場合は早めに支払っておくことが大切です。
売却活動の期間に余裕がある
任意売却には期限があり、競売開札日の直前までに完了できなければ成立しません。
一般的な不動産売却と違って、任意売却には時間の余裕がありません。
目安としては、代位弁済から約1年以内に手続きを完了させる必要があります。
そのため、計画的に進めることや信頼できる業者のサポートを受けることが大事です。
任意売却をできないといずれは競売に

債権者の同意を得られなかったり、期限内に任意売却が完了できなかった場合、自宅は競売にかけられます。
売却代金が住宅ローン残債を上回る「アンダーローン」であれば、ローンを完済できるため、任意売却の必要はありません。
競売の場合は、物件の売却価格が相場の5〜7割程度になり、諸費用の支払いに自己資金の持ち出しが必要になります。
裁判所主導で手続きが進み強制退去となる上に、官報や競売物件情報サイトに情報が掲載されるため、事情を知られる可能性があります。
競売を回避するためには、債権者の同意を得て期限までに任意売却の手続きをすべて完了させることが必要です。
任意売却の実績が豊富な業者に相談しながら進めることで、成功確率を高めることができます。
あわせて読みたい
任意売却の流れ
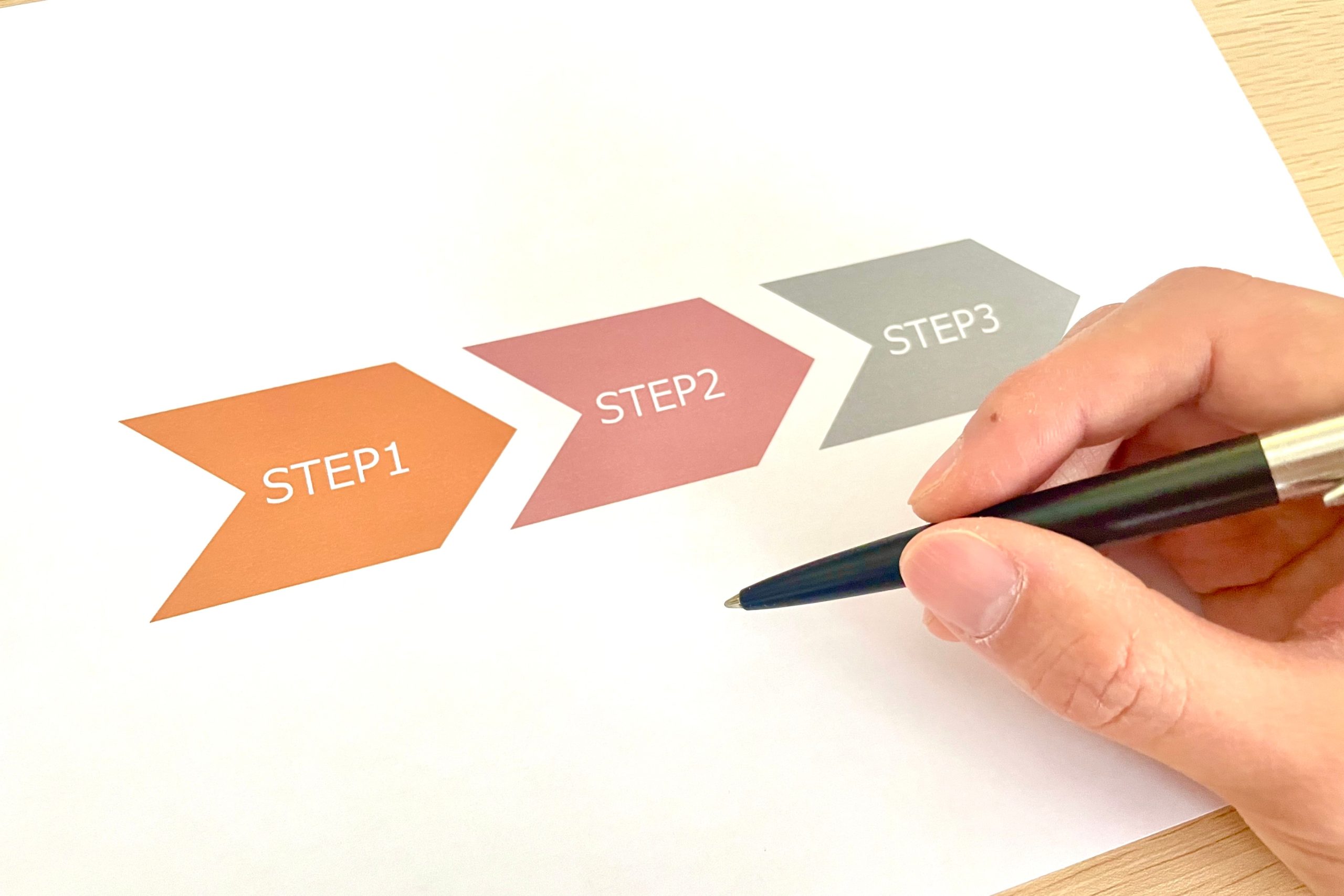
任意売却は、競売の開札日直前までに売却や手続きを完了させる必要があります。
間に合わなかった場合は、自宅は競売にかけられることになります。
競売になると、任意売却よりも不利な条件で売却される上に、周囲に事情が知られる可能性もあります。
事前に任意売却の流れを把握して、スムーズに進められるようにしましょう。
1.住宅ローンの滞納
住宅ローンを数ヶ月滞納すると、金融機関から督促状や催告書が届きます。
督促状や催告書が届いた時点で滞納分を支払うことができれば、競売や任意売却は回避できます。
しかし、支払いができない場合は、競売や任意売却へと進むことになります。
2.期限の利益喪失
督促後も滞納が続く場合は、期限の利益を喪失することになり、金融機関から住宅ローンの一括返済を求められます。
また、保証会社が金融機関に代わって支払いを行う「代位弁済」によって、債権者が金融機関から保証会社へと変わります。
あわせて読みたい
3.専門業者への相談
任意売却は債権者との交渉や期限内での売却が必要なため、実績豊富な専門業者に相談することが重要です。
専門業者のアドバイスやサポートを受けながら進めることで、債権者との交渉や期限内での売却が成功する可能性が高くなります。
逆に、任意売却の実績がほとんどない業者に依頼すると、債権者の同意が得られなかったり、期限内での売却が間に合わなくなり、競売になるリスクが高まるため注意が必要です。
あわせて読みたい
4.不動産価格の査定
自宅の査定を受けることで、おおよその売却金額がわかります。
任意売却は市場相場に近い価格で売却できるため、競売より残債を減らしやすいのが特徴です。
そのため、住宅ローンの残債も競売より多く減らすことができます。
あわせて読みたい
5.債権者との交渉
債権者の同意が得られなければ任意売却は成立しません。
交渉が難航することも多いため、売主自身で交渉したり実績のない業者に依頼すると、断られるリスクが高くなります。
債権者との交渉は非常に重要なため、実績豊富な専門業者に相談しましょう。
6.売却活動
債権者の同意を得た後は、条件の確認をして売却活動がスタートします。
早期売却を実現するためには、売主の協力的な姿勢が大切です。
7.清算・引き渡し
買主が決まったら売買契約を締結します。
契約後、決済と引き渡しとなり、売却代金をもとに住宅ローンを返済します。
売却にあたり仲介手数料や印紙税、抵当権抹消登記費用などが発生しますが、これらの費用を売却代金から支払うことが可能です。
あわせて読みたい
あわせて読みたい
まずは、お早めにご相談ください。

任意売却を成功させるには、実績豊富で信頼できる専門業者に相談することが不可欠です。
専門業者は、金融機関との交渉や期限内に売却するための多くのノウハウを持っているため、比較的スムーズに進めることができます。
現在、任意売却を検討されている方は、当サイトを運営する一般社団法人全国任意売却協会にぜひご相談ください。
解決事例一覧
「ゆとりローン」の落とし穴。定年後に膨らんだ返済負担から任意売却で脱出したケース
Tさんは40代で新築マンションを購入。当時主流だった「ゆとりローン」を利用し、当初は金利のみの支払いで月々の負担も少なく...
2軒分住宅ローン負担増、任意売却と自己破産でゼロ負担に再出発したケース
Tさんは、新しい住宅を購入する際、以前所有していた戸建の残債に新築の住宅ローンを上乗せして融資を受け、2軒分のローンを抱...
40代で会社が倒産、過労と離婚を経て任意売却で生活を立て直したケース
Dさんは東京都清瀬市で不動産関連会社を経営していましたが、業績悪化により会社は倒産。借金こそなかったものの、その直後に過...
50歳でうつ病を発症、「住宅ローンが払えない」状況から任意売却で再出発したケース
Bさんは群馬県高崎市で28年間勤務していましたが、50歳のときにうつ病を発症。1年後には早期退職となり、失業保険も切れた...