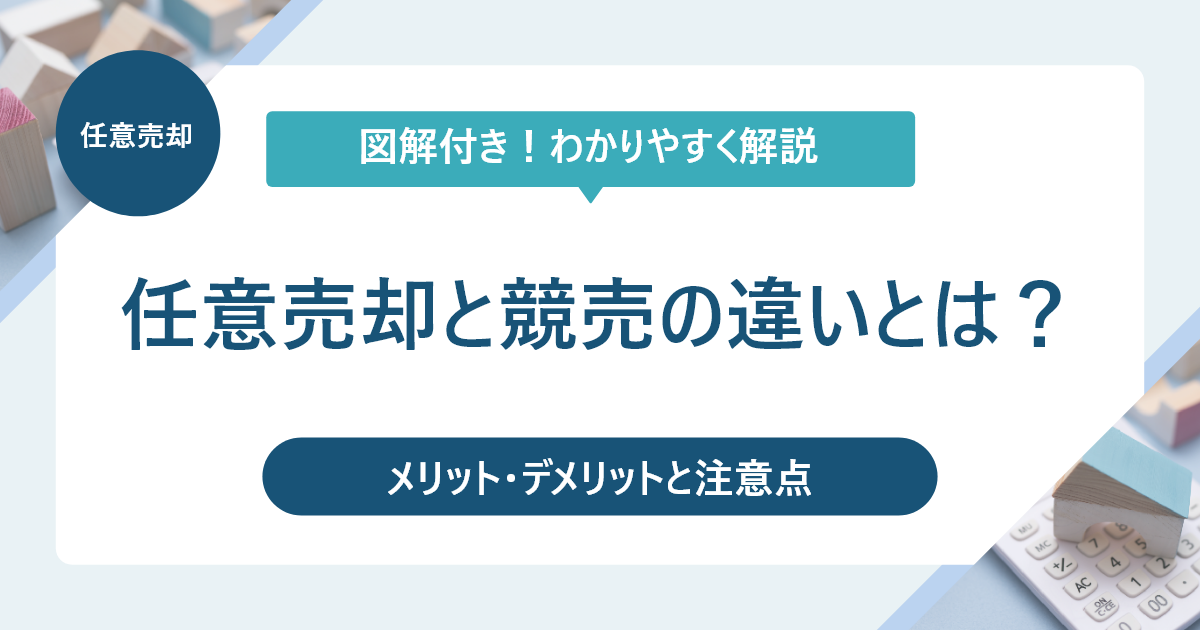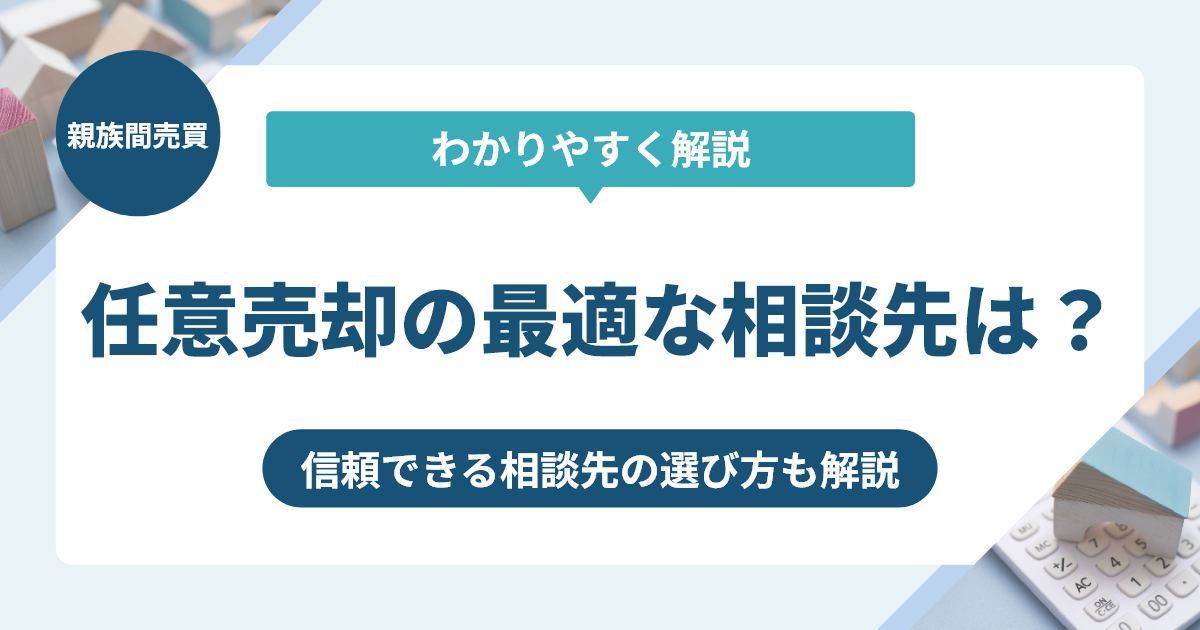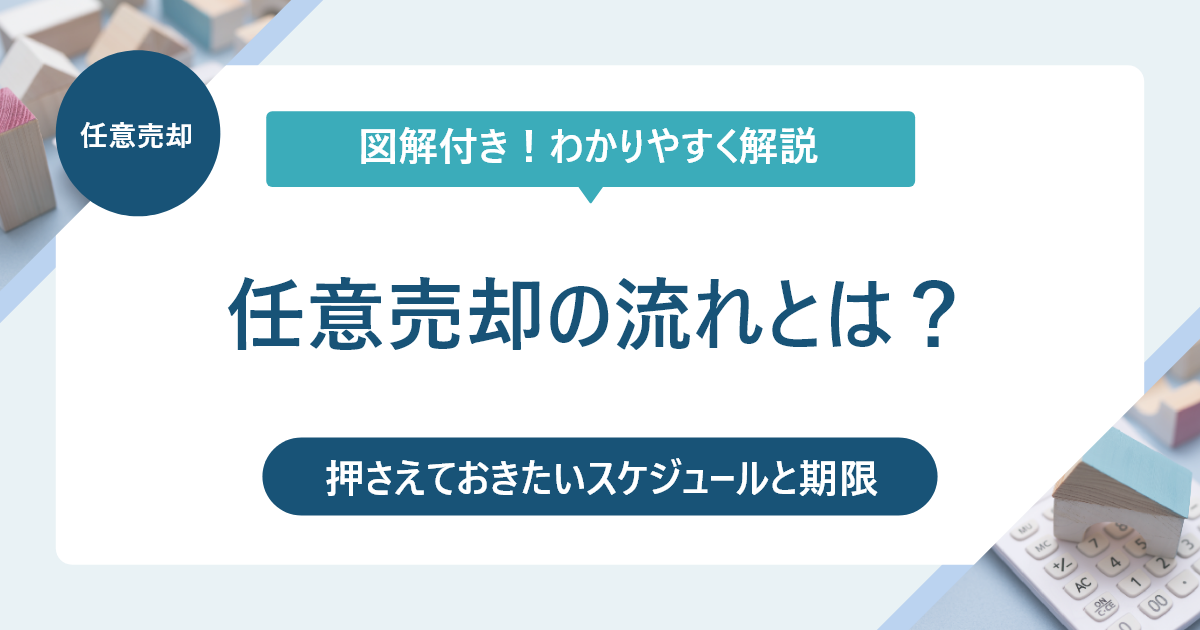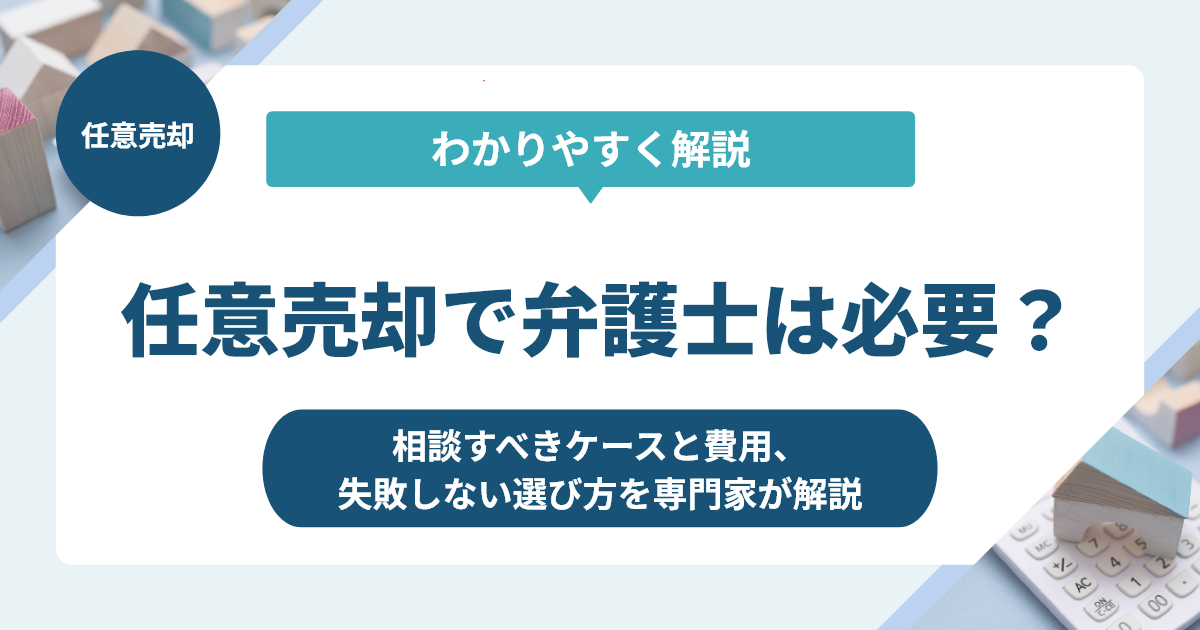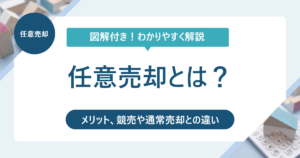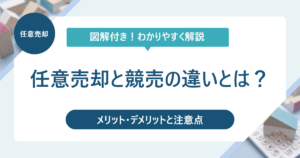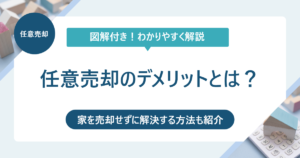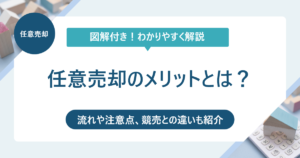任意売却にかかる費用は?持ち出し原則0円の仕組みと内訳を解説
更新日 2025-12-30
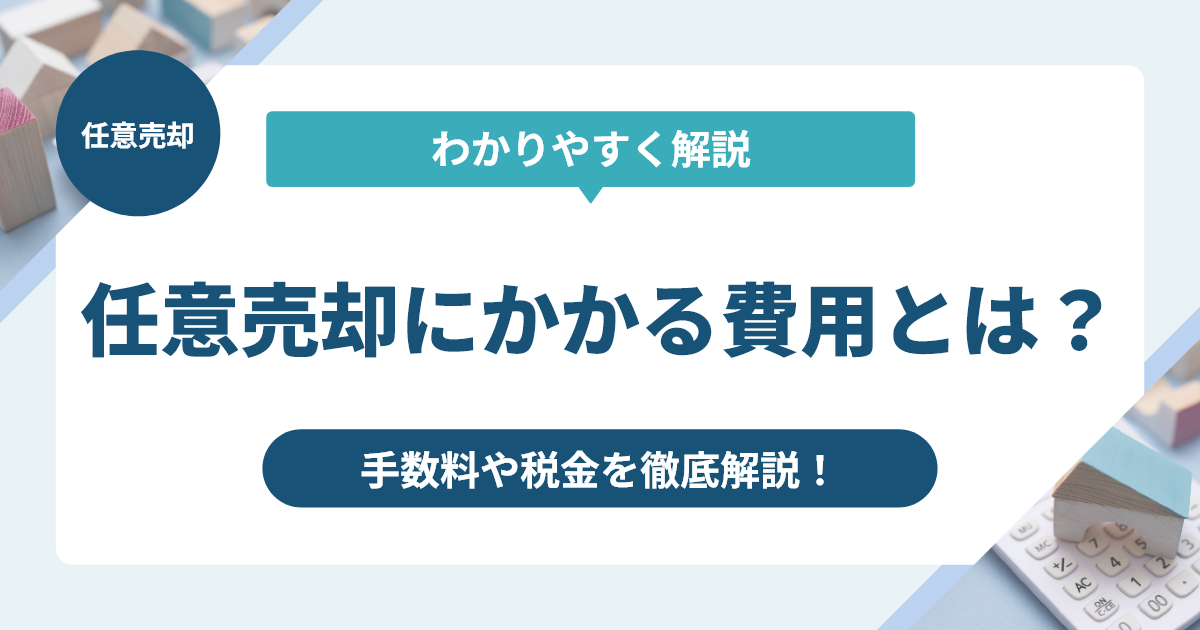

任意売却を検討する中で「実際どんな費用がかかるの?」「どれくらい必要なの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
任意売却では、仲介手数料や住宅ローンの一括返済手数料など、さまざまな費用が発生します。事前に把握しておくことで、無理のない資金計画を立てやすくなるのがポイントです。
そこで本記事では、任意売却にかかる具体的な費用や税金、競売との費用負担の違いについて解説します。
任意売却にかかる費用

任意売却を検討する際、「費用を自分で用意する必要があるの?」と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、ほとんどの場合、売主様が手持ちの現金から費用を支払う必要はありません。
なぜなら、任意売却にかかる諸費用は、物件の売却代金から差し引く(配分する)形で支払うことを、債権者(金融機関)との交渉によって認めてもらえるためです。住宅ローンの返済が困難な状況を理解した上で、売却に必要な経費として処理されます。
ただし、例外的に持ち出しが必要となるケースも存在します。まずは、どのような費用が発生するのか、そして「持ち出しが不要なケース」と「必要なケース」について詳しく解説します。
住宅ローン危険度診断


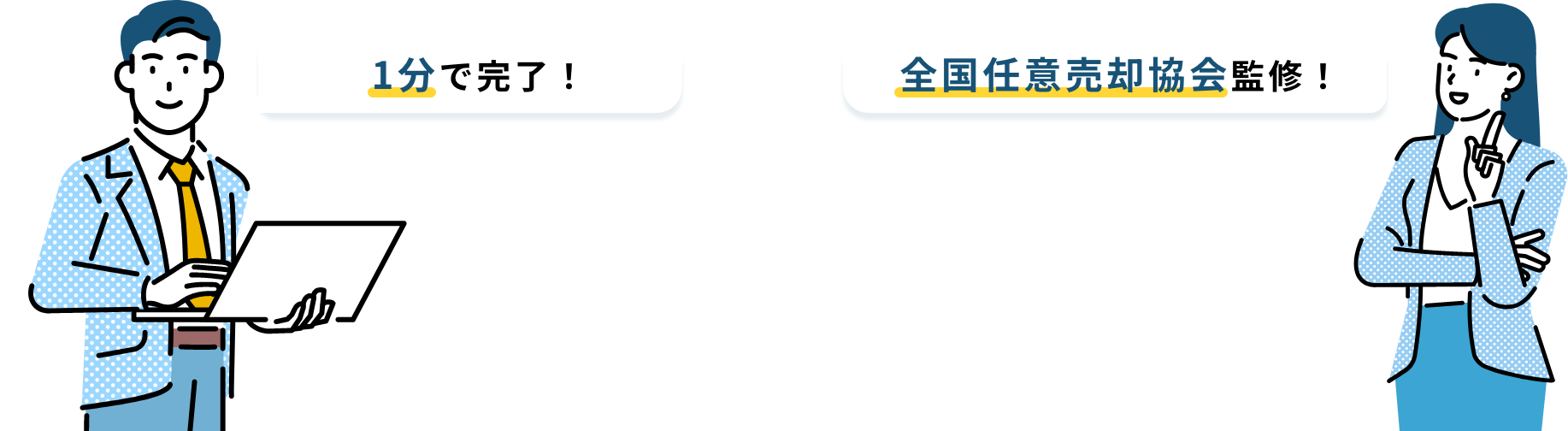
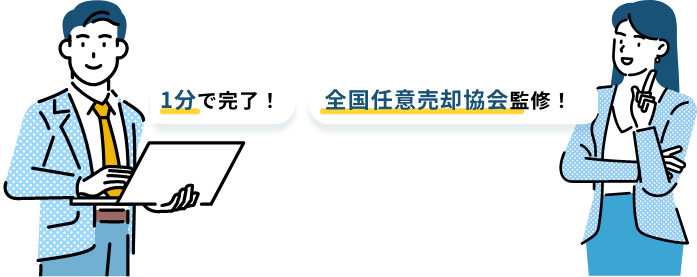
任意売却で発生する主な費用
任意売却では、通常の不動産売却と同じく、以下のような費用が発生します。これらは基本的にすべて売却代金から支払われます。
- 仲介手数料: 売却が成立した際に不動産会社へ支払う報酬です。法律で上限が「売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税」と定められています(売買価格400万円超の場合)。
- 抵当権抹消登録費用: ローンを完済し、不動産に設定された抵当権を抹消するための登記費用です。登録免許税(不動産1件につき1,000円)と、手続きを代行する司法書士への報酬が含まれます。
- 印紙税: 不動産売買契約書に貼付する収入印紙の代金です。売買価格によって異なり、例えば1,000万円超5,000万円以下の場合は1万円です(軽減税率適用時)。
- ローンの一括返済手数料: 金融機関によっては、ローンを繰り上げて一括返済する際に手数料(無料〜3万円程度)がかかる場合があります。
- 滞納分の費用: マンションの管理費・修繕積立金や、固定資産税などを滞納している場合、これらの費用も売却代金から清算されます。
住宅ローン危険度診断


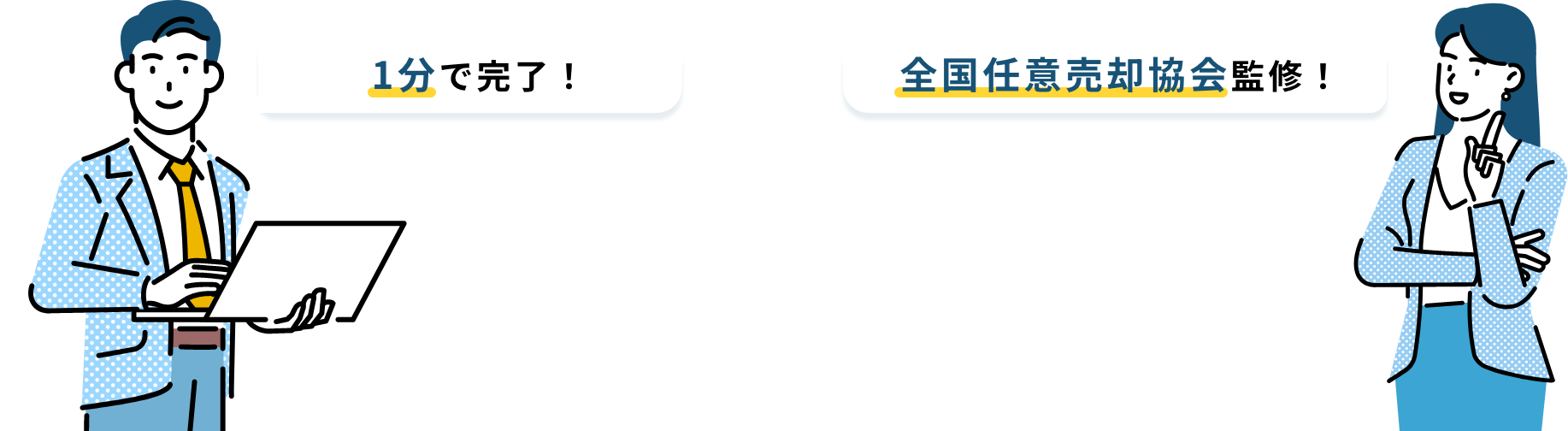
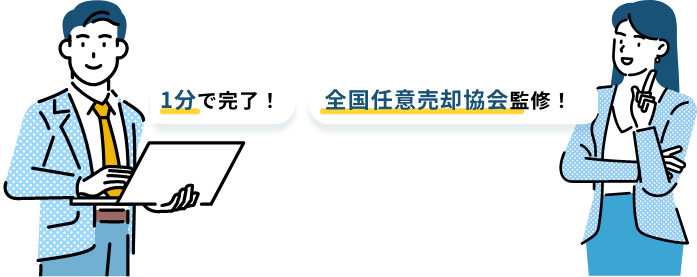
費用の持ち出しが「不要な」ケース(原則)
前述の通り、任意売却では売主様の手元資金がなくても手続きを進められるのが一般的です。
債権者(金融機関)は、競売よりも任意売却のほうが高く売れ、より多くの金額を回収できることを理解しています。そのため、売却を成立させるために必要な経費(仲介手数料や登記費用、滞納管理費など)を売却代金から支払うことを認めてくれるのです。
これらの費用は、売買が成立し、物件の引き渡し(決済)が行われる日に、売却代金から関係各所へ直接支払われるため、売主様が事前に準備したり、立て替えたりする必要はありません。
費用の持ち出しが「必要な」ケース(例外)
原則として持ち出しは不要ですが、以下のような特殊なケースでは、売主様ご自身での支払いが必要になることがあります。
1. 売却益(譲渡所得)が出た場合
任意売却であっても、売却価格がローン残高や取得費を上回り、利益(譲渡所得)が出た場合は、その利益に対して「譲渡所得税(所得税・住民税)」が課税されます。
この税金は、売却代金から配分される「経費」とはみなされず、売主様が売却の翌年に確定申告を行い、ご自身で納税する必要があります。
ただし、ご自身が住んでいたマイホームの売却であれば、「3,000万円の特別控除」という特例を使えることが多く、利益が3,000万円以下であれば実質的に課税されません。任意売却のケースでこの税金が発生することは稀です。
2. 債権者との交渉が難航した場合
非常に稀なケースですが、債権者が一部の費用(例:高額すぎる滞納管理費の一部など)の配分を認めなかったり、任意売却の経験が浅い業者に依頼して交渉に失敗したりすると、売主様に一部負担が求められる可能性もゼロではありません。
こうした事態を避けるためにも、債権者との交渉ノウハウが豊富な任意売却の専門家に依頼することが非常に重要です。
住宅ローン危険度診断


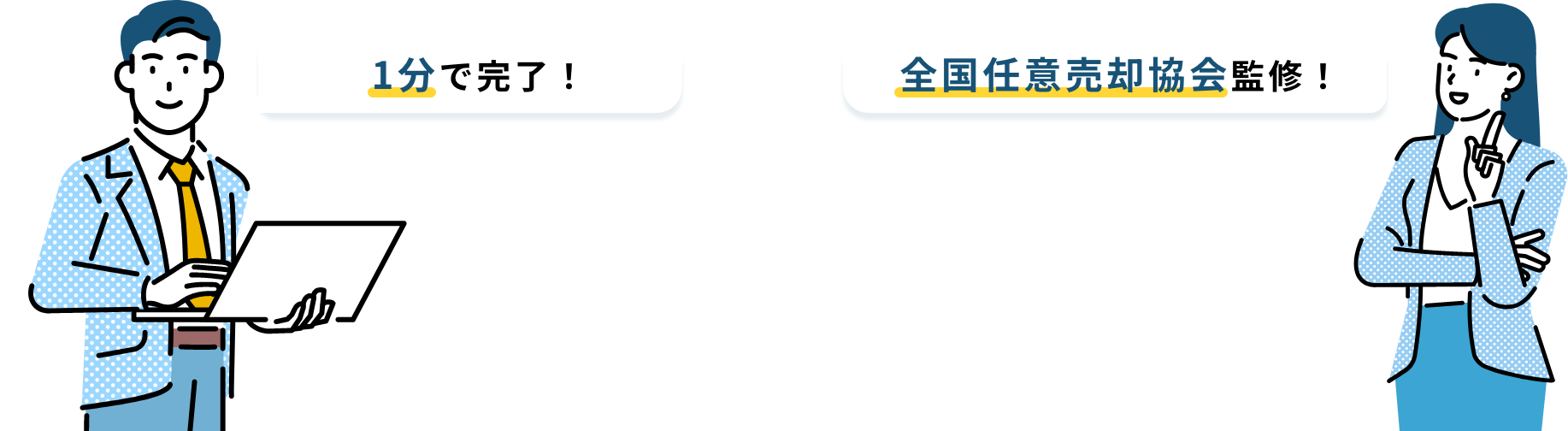
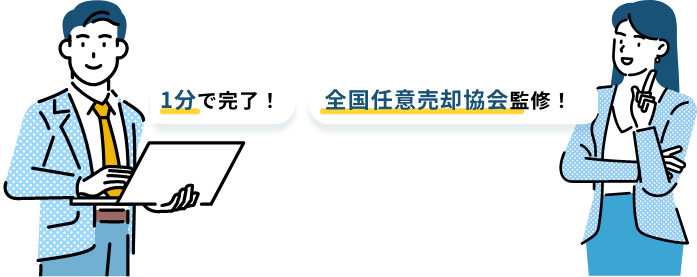
任意売却と競売の費用負担の違い

任意売却では、仲介手数料などの費用が発生しますが、競売では申立手数料や予納金といった費用がかかります。特に予納金は、調査や手続きにかかる費用で、物件の価格によっては100万〜200万円かかることもあります。
また、任意売却は市場相場に近い金額で売却できる可能性がありますが、競売ではその5〜7割程度になることが一般的です。どちらの場合も住宅ローンの完済が求められますが、より高く売却できる任意売却のほうが金銭的に有利といえるでしょう。
あわせて読みたい
住宅ローン危険度診断


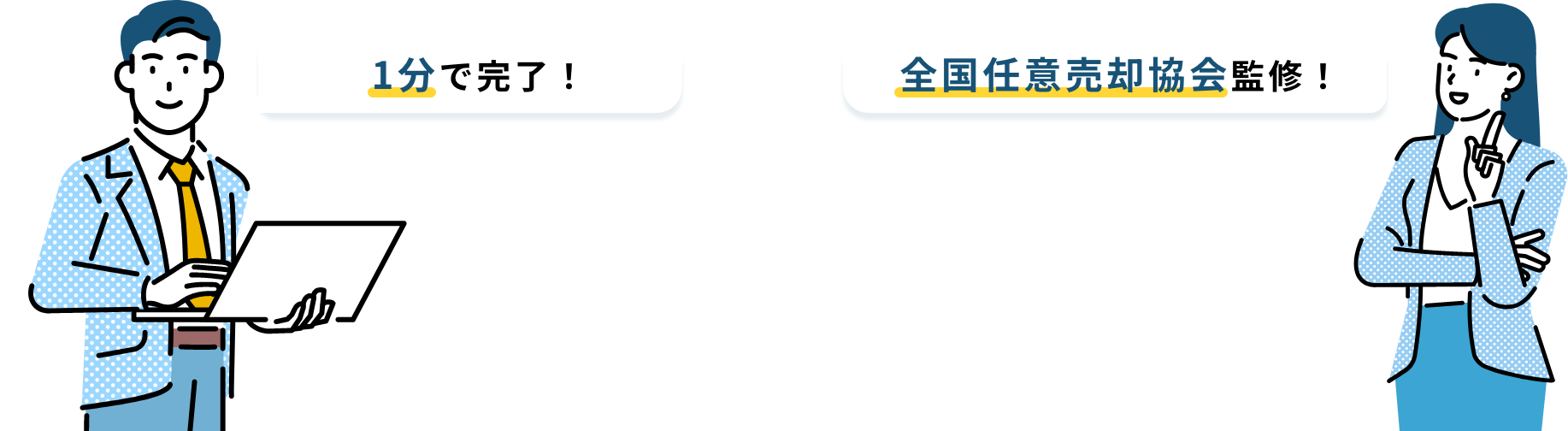
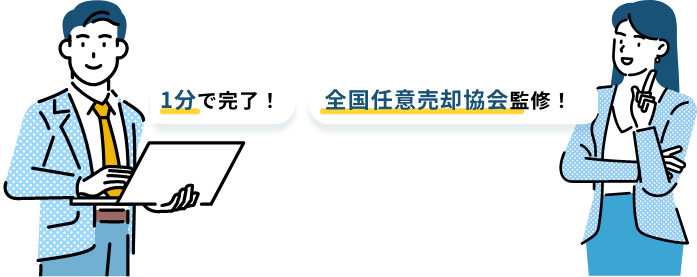
任意売却を成功するためのコツ

任意売却を成功させるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。例えば、一般的な不動産会社ではなく任意売却の実績が豊富な専門業者に依頼することで、的確なアドバイスや手厚いサポートで安心して進めることができます。
信頼できる実績豊富な業者を選ぶ
任意売却では金融機関との交渉が必要で、売却までの期間にも制限があります。そのため、実績が豊富で信頼できる専門業者のサポートを受けることが大事です。経験の浅い業者に依頼すると、交渉が難航したり、売却が間に合わず競売にかけられるリスクが高まります。一方、実績が豊富な業者であれば、ノウハウを活かして適切に対応してくれるため、安心して任意売却を進めることができます。
あわせて読みたい
住宅ローン危険度診断


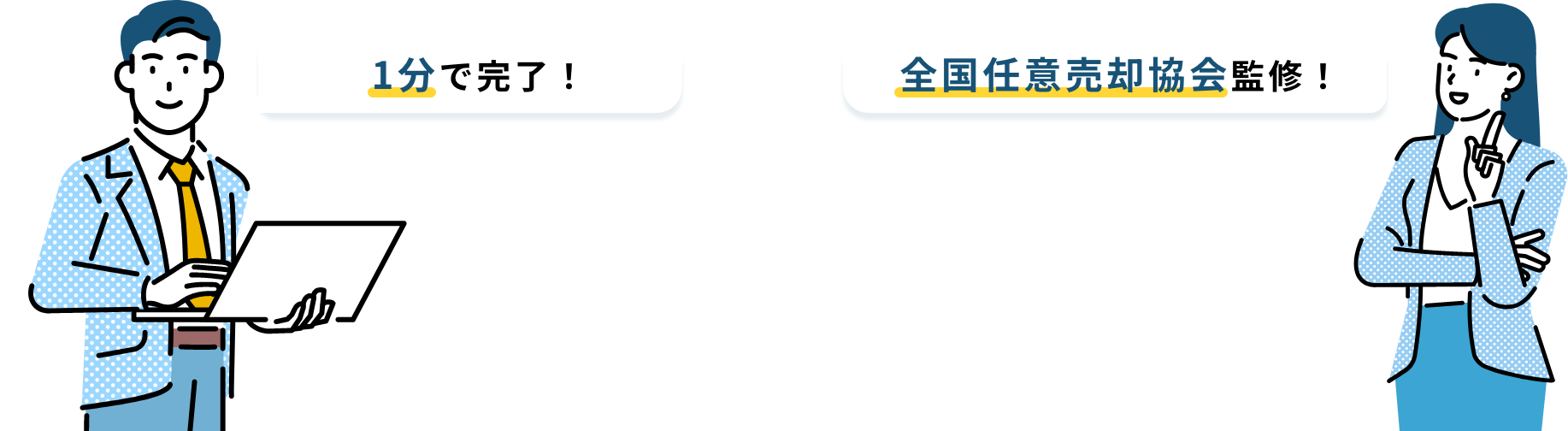
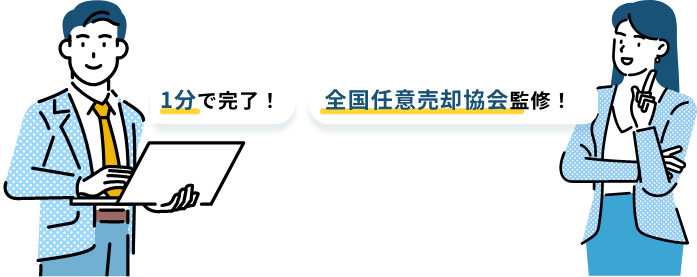
早めに動いてスケジュールに余裕をもたせる
任意売却は、競売開札日の1〜2日前までにすべての手続きを完了させる必要があります。通常の不動産売却よりもスケジュールが厳しいため、できるだけ早く売却活動を開始することが大切です。
あわせて読みたい
売却活動には積極的に取り組む
少しでも良い条件で早期に売却を完了させるためには、売主自身が積極的に売却活動に協力することが大切です。特に内覧対応は重要で、買主の印象を左右し、購入意欲に大きな影響を与えます。不動産会社と相談しながら、物件の見せ方を工夫したり内覧前に丁寧に掃除をするなど、できる限り良い印象を与えるよう心掛けることが大事です。
住宅ローン危険度診断


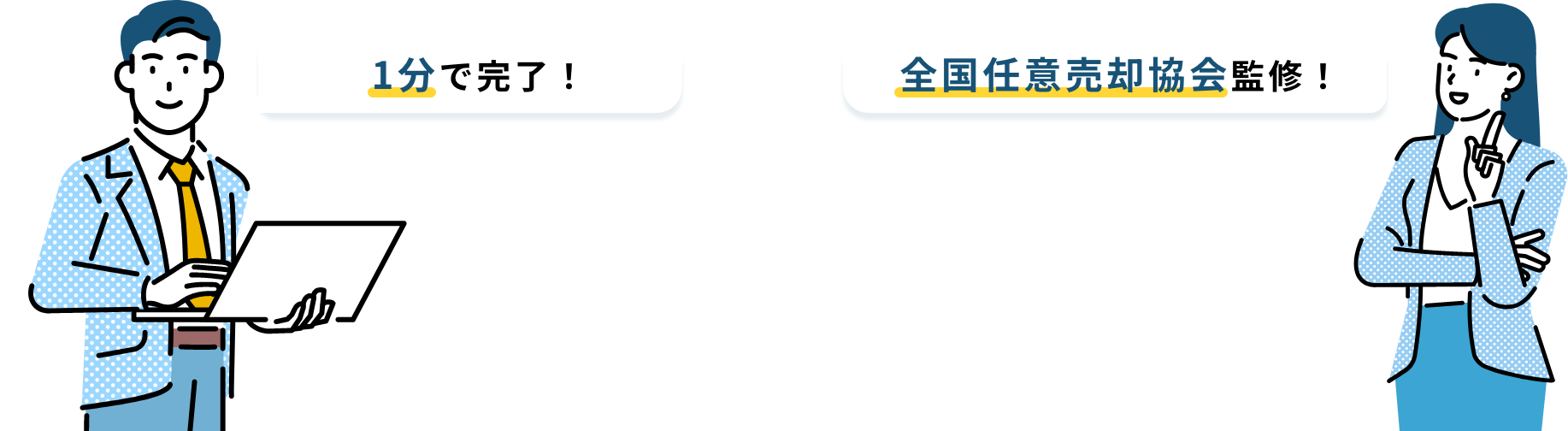
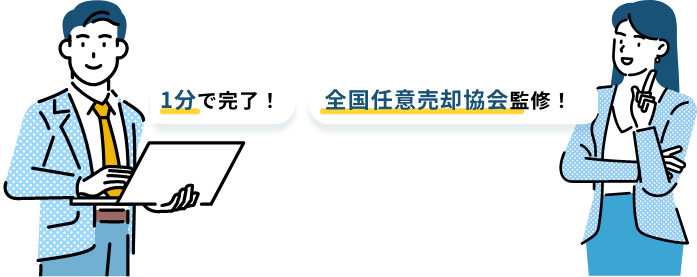
任意売却の費用に関するよくある質問
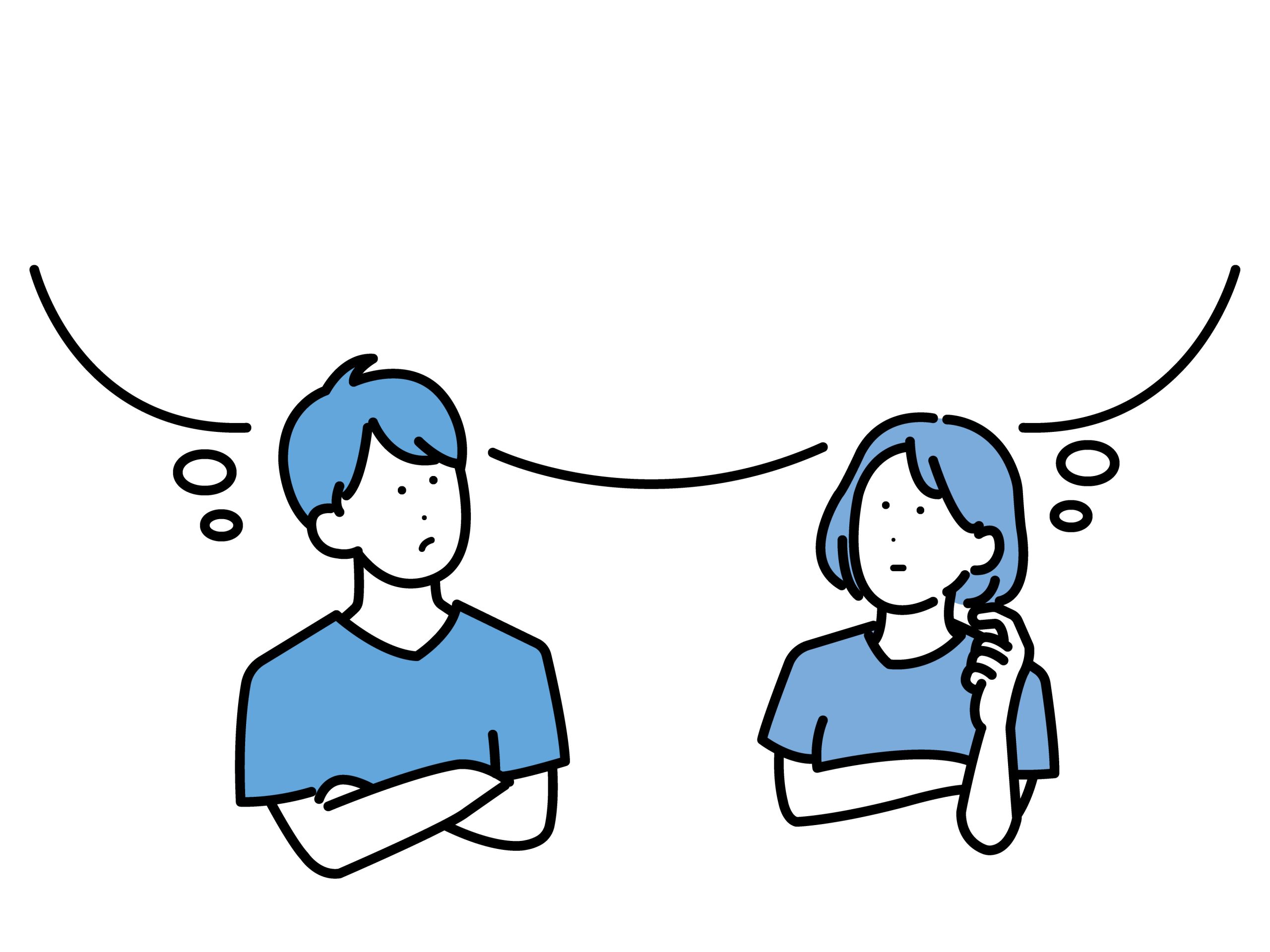
任意売却の費用について、よくある質問や疑問を把握しておくことも大切です。
任意売却の相談にはどれくらいの費用がかかりますか?
相談先によって費用が異なります。例えば、弁護士やファイナンシャルプランナーに相談する場合、初回相談は無料のところも多いですが、2回目以降は費用が発生することが一般的です。一方で、任意売却の専門業者に相談する場合、何度相談しても無料で対応してくれることもあります。
任意売却に弁護士費用はかかりますか?
弁護士にサポートを依頼する場合、事務所で決められた費用が発生します。そのため、相談する前に費用を確認しておいたほうがよいでしょう。また、不動産を売却する際には、不動産会社に支払う仲介手数料などの費用もかかります。
住宅ローン危険度診断


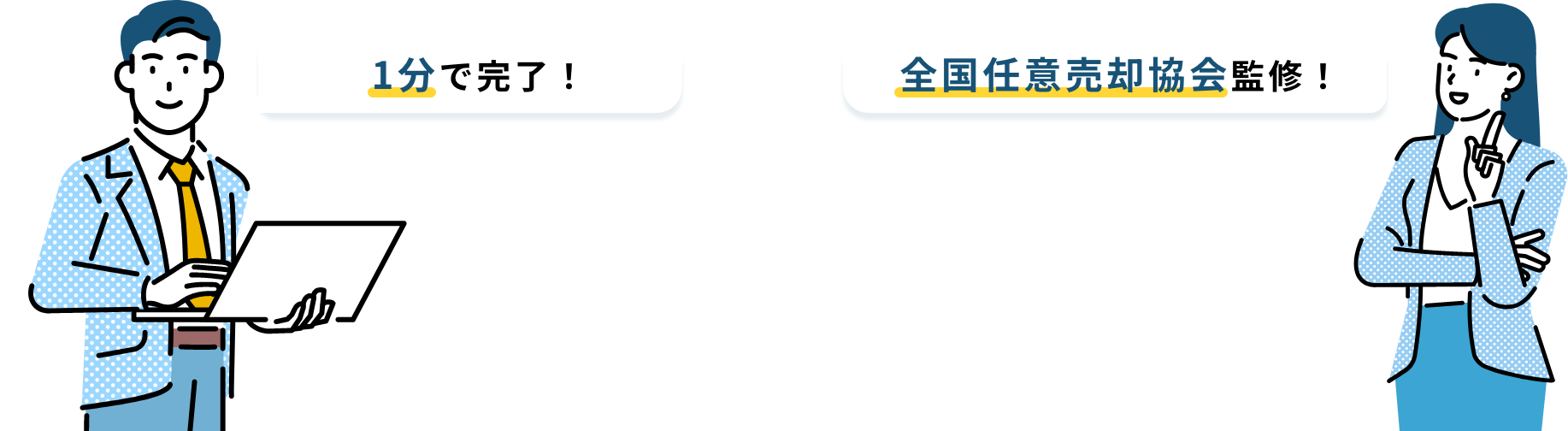
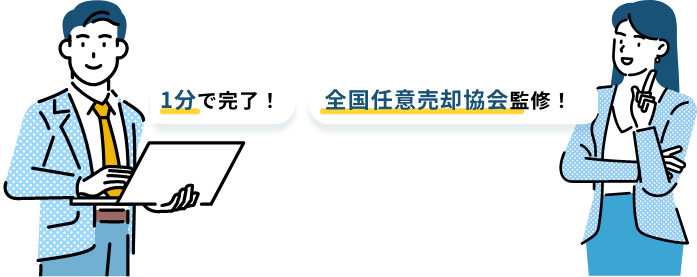
任意売却は専門家にご相談ください

任意売却の際には、仲介手数料や印紙代、抵当権抹消登記費用などが発生します。事前にどのような費用がかかるのかを把握しておくことで、売却後の資金計画を立てやすくなります。
また、任意売却を進めるには金融機関との交渉や期限があるため、実績が豊富な任意売却の専門家のサポートを受けることで安心して進めることができます。
現在、競売や任意売却の可能性がある方は、当サイトを運営する一般社団法人全国任意売却協会にぜひご相談ください。状況に応じた的確なアドバイスやサポートを行います。
解決事例一覧
「ゆとりローン」の落とし穴。定年後に膨らんだ返済負担から任意売却で脱出したケース
Tさんは40代で新築マンションを購入。当時主流だった「ゆとりローン」を利用し、当初は金利のみの支払いで月々の負担も少なく...
2軒分住宅ローン負担増、任意売却と自己破産でゼロ負担に再出発したケース
Tさんは、新しい住宅を購入する際、以前所有していた戸建の残債に新築の住宅ローンを上乗せして融資を受け、2軒分のローンを抱...
40代で会社が倒産、過労と離婚を経て任意売却で生活を立て直したケース
Dさんは東京都清瀬市で不動産関連会社を経営していましたが、業績悪化により会社は倒産。借金こそなかったものの、その直後に過...
50歳でうつ病を発症、「住宅ローンが払えない」状況から任意売却で再出発したケース
Bさんは群馬県高崎市で28年間勤務していましたが、50歳のときにうつ病を発症。1年後には早期退職となり、失業保険も切れた...