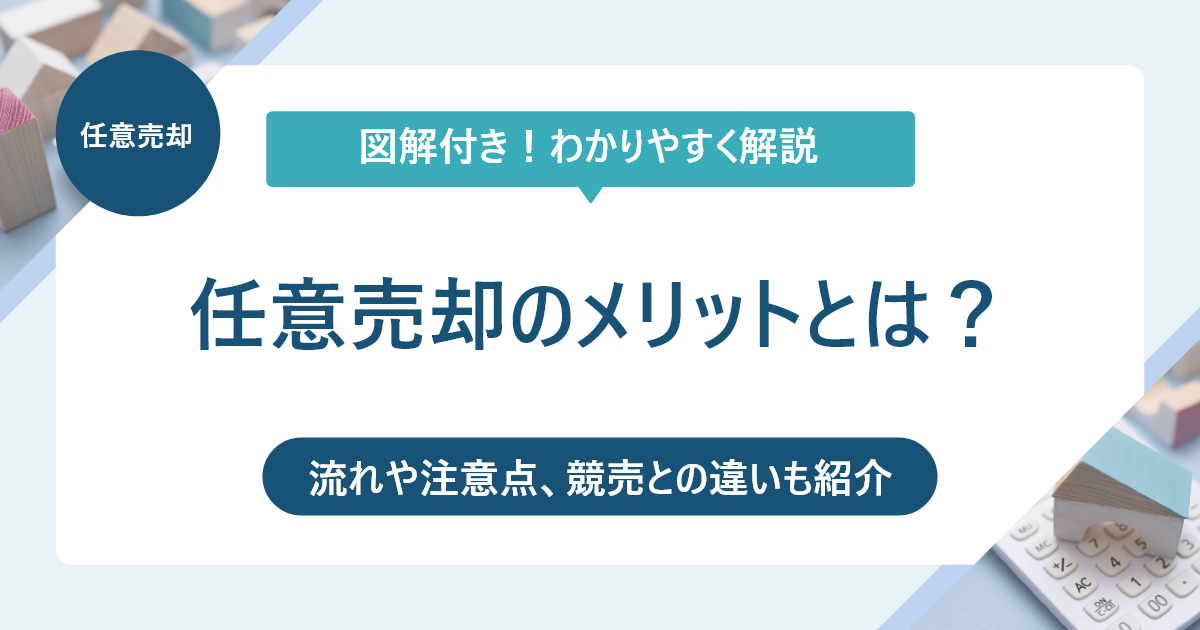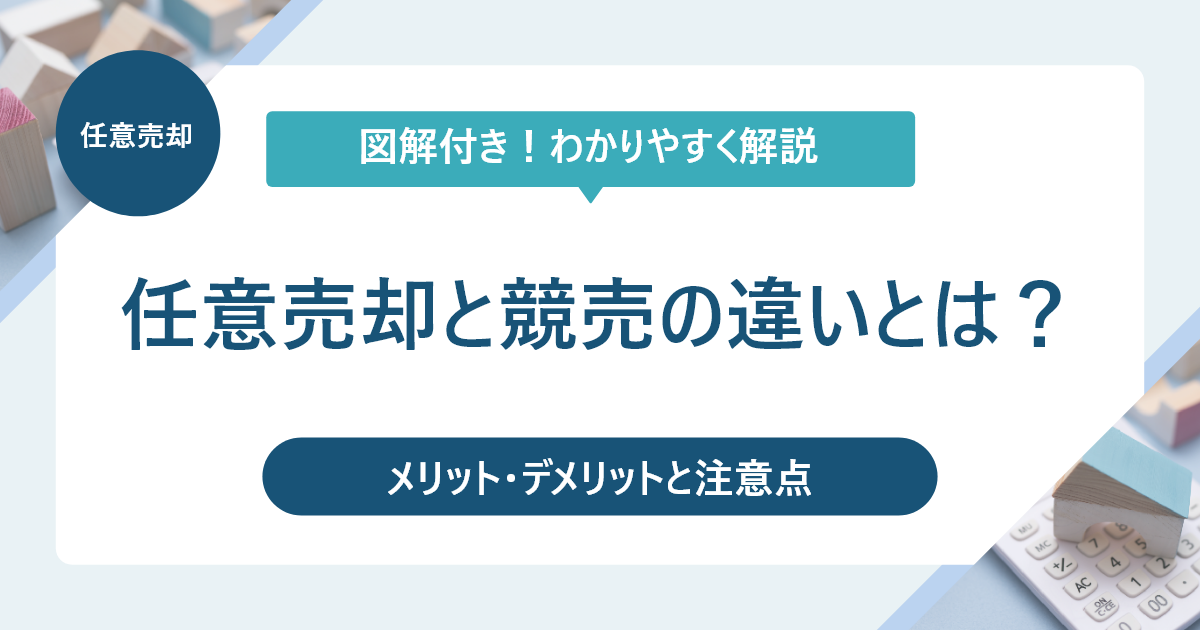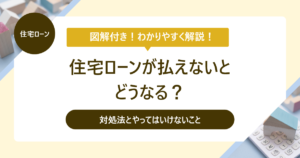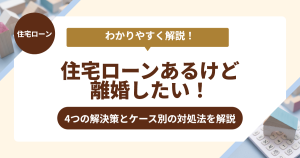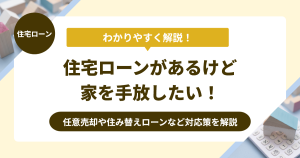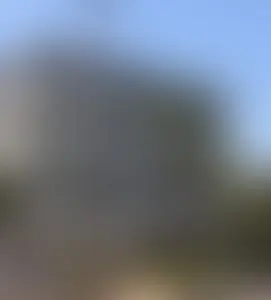住宅ローンの連帯保証人が死亡したら?一括返済を回避し家を守る方法を解説!
更新日 2025-12-10
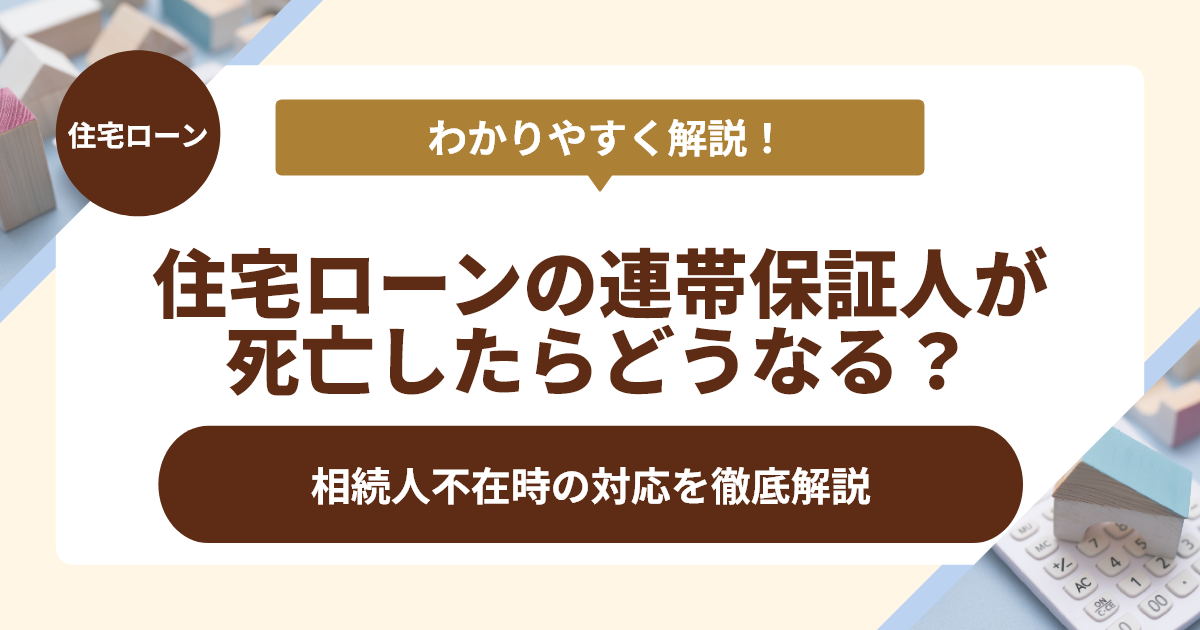

「連帯保証人が亡くなってしまった…銀行に言ったら一括返済を求められる?」
「保証人の代わりが見つからない場合、家はどうなるの?」
住宅ローンの連帯保証人が亡くなると、主債務者(契約者)は大きな不安に襲われます。
結論から言えば、主債務者が返済を続けている限り、即座に家を失うことはありません。
しかし、対応を誤ったり放置したりすると、銀行から契約違反を問われ、最悪の場合、自宅の売却(競売)を迫られるリスクがあります。
この記事では、連帯保証人が亡くなった時にやるべき手続きと、代わりの保証人がいない場合の対処法、そして「最悪の事態を避けるための解決策(任意売却)」について、専門家がわかりやすく解説します。
1. 連帯保証人が亡くなったら?まずやるべき2つのこと

パニックにならず、以下の手順で冷静に対応しましょう。
① 金融機関への連絡(契約上の義務)
住宅ローンの契約約款には、「連帯保証人の死亡」などの重要事項が生じた場合、速やかに銀行へ報告する義務が記されています。
黙っていても、銀行は定期的な調査や相続手続きの過程でいずれ把握します。隠していたことがバレると「信頼関係の破壊」とみなされ、一括返済を求められるリスクが高まるため、正直に報告しましょう。
② 「団信」の確認(基本は対象外)
「連帯保証人が亡くなれば、団信(団体信用生命保険)でローンが消えるのでは?」と期待される方がいますが、残念ながら対象外のケースがほとんどです。
団信はあくまで「主債務者(借りた本人)」の生命保険です。ただし、ペアローンや連帯債務で、それぞれが団信に入っている場合は適用されることもあるため、念のため確認してください。
2. 連帯保証人の地位は「相続」される
「人が亡くなったら保証契約も終わる」わけではありません。
連帯保証人の地位(借金を肩代わりする義務)は、「マイナスの財産」として法定相続人に引き継がれます。
| 相続のパターン | 結果 |
|---|---|
| 単純承認 | 相続人(配偶者や子供など)が、新たな連帯保証人になります。 |
| 相続放棄 | その相続人は保証人になりません。 (※プラスの遺産も一切受け取れなくなります) |
もし相続人が「親の借金なんて背負いたくない」と相続放棄をした場合、あるいは相続人が一人もいない場合、「連帯保証人が不在」という状態になります。
これが、主債務者にとって最も危険な状況です。
3. 保証人がいない!銀行の対応とリスク

相続放棄などで連帯保証人がいなくなった場合、銀行からは以下の要求が来ます。
要求①:代わりの連帯保証人を立ててください
原則として、亡くなった方と同等の信用力を持つ代わりの人を求められます。
しかし、他人の巨額のローンの保証人になってくれる人など、そうそう見つかるものではありません。
要求②:残高を一括で返済してください
代わりの人が用意できない場合、銀行は「契約違反(期限の利益喪失)」として、ローン残高の全額一括返済を求めてくることがあります。
これができなければ、最終的に自宅は「競売」にかけられ、強制的に処分されてしまいます。
4. 家を守る、あるいは有利に手放すための解決策
「代わりの保証人もいない、一括返済もできない」
そんな八方塞がりな状況でも、諦める必要はありません。以下の解決策を検討しましょう。
解決策①:別担保や保証会社の利用を交渉する
人的な保証人の代わりに、別の不動産を担保に入れたり、保証会社を利用(保証料が必要)したりすることで、銀行に納得してもらえる可能性があります。
解決策②:任意売却(救済措置)
一括返済を迫られ、競売が避けられない状況になった場合の「切り札」です。
任意売却(にんにばいきゃく)とは、銀行と話し合い、市場価格に近い金額で自宅を売却する方法です。

任意売却のメリット
- 競売を回避できる:市場価格で売れるため、競売よりも残る借金(残債)を大幅に減らせます。
- 引越し代の確保:交渉次第で、売却代金から引越し費用を捻出できる可能性があります。
- 住み続けられる可能性:投資家に家を買ってもらい、家賃を払って住む「リースバック」と組み合わせることも可能です。
あわせて読みたい
あわせて読みたい
まとめ:焦らず、まずは専門家に相談を

連帯保証人の死亡は、誰にとっても想定外の事態です。
銀行から厳しい連絡が来ると焦ってしまいますが、まずは落ち着いて専門家に相談してください。
「代わりの保証人がいないけれど、家を残したい」
「競売だけは避けたい」
一般社団法人 全国任意売却協会では、こうした複雑な事情を抱えた方からのご相談を多数解決してきました。
銀行との交渉や、相続問題の整理など、あなたが平穏な生活を取り戻すためのサポートを全力で行います。相談は無料です。
解決事例一覧
「ゆとりローン」の返済額倍増と教育費が直撃!計画的な任意売却で不安を乗り越えたケース
福岡市にお住まいのSさん(52歳)は、新築マンションを購入した際に「ゆとりローン」を利用しました。当初の月々返済額は11...
「住宅ローンを3人で組む」リスクが表面化。親子3人名義の家を任意売却したケース
Kさんは母と妹との3人家族で、夢だったマイホームを親子3人名義で購入。住宅ローンを3人で組む(収入合算)ことで審査を通し...
「旦那が借金を残して死んだら…」住宅ローンと不明な債務を相続放棄と任意売却で解決した事例
Tさんはご主人を病気で亡くされましたが、「旦那が借金を残して死んだらどうなるか」という不安通り、借金の有無も不明なまま働...
2軒分の住宅ローンと高額な債務を任意売却と自己破産でゼロに!再スタートを成功させたケース
Tさんは、新しい住宅を購入する際、以前所有していた戸建の残債に新築の住宅ローンを上乗せして融資を受け、2軒分のローンを抱...
50歳でうつ病を発症、「住宅ローンが払えない」状況から任意売却で再出発したケース
Bさんは群馬県高崎市で28年間勤務していましたが、50歳のときにうつ病を発症。1年後には早期退職となり、失業保険も切れた...
うつ病で働けず、住宅ローンがネックで生活保護も不可に。任意売却と自己破産で支援を確保したケース
Tさんは原因不明の体調不良からうつ病を発症し、経営していた会社を閉鎖。病気の悪化に加え、奥様が脳梗塞で半身不随となり、夫...